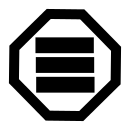| TOPページへ戻る | |||||
| 兵庫県 |
明石市 |
− | − | 播磨国 | |
| 稲爪神社 | - | ||||
| 式内社 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 郷社 | |||||
| 囚われた屈辱は反撃の嚆矢だ 明石浜に鉄人を穿つ紅蓮の弓矢 | |||||
|
※イメージです |
古代日本に襲来した謎の鉄鎧の巨人8000騎。これを撃退した英雄が小千益躬という武将である。彼は大山祗神(三嶋大明神)に必勝祈願を行った。そして明石の浜での決戦。大山祗神の加護により稲妻が光ると、敵の鉄巨人が怯む。その間隙に巨人の弱点を攻撃することに成功し、奇跡的に巨人軍団を撃破したのである。
そんなわけで戦勝の地に大山祗神を祀る神社を建て、「稲妻大明神」と称した。のちにこれが転嫁して「稲爪神社」というようになったという。
延喜式の神名帳では「伊和都比売神社」と言うのがあり、一説ではこの神社を指すもと考えられている。社誌では、この「伊和都比売神社」はいまの本殿の西に鎮座しており、いまは合祀されている。
|
所在 |
兵庫県明石市大蔵本町 |
|
創建 |
推古天皇の治世(593-628) |
|
祭神 |
大山祗神 |
| 面足神、惶根命 ほか | |
| 賀志波比売命は開運延命・病気平癒・海上安全の神とされている。『日本書紀』や『古事記』に頻繁に登場するようなポピュラーな神ではないようだ。この津峯山の主神として祀られている以外には、あまり情報がない。 |
|
西暦593年から628年に在位した推古天皇の時代に小千益躬(おちのますみ)という武将が創建したと伝わる。 この時代に、「三韓」から「鉄人」が日本へ侵攻してきた。中国の南北朝時代(439〜588)・唐代(618-907)には高句麗・百済・新羅のことを三韓と称しており、『日本書紀』もこれに準じるそうだ。最近は、これらよりも古い時代に朝鮮半島南部にあったとされる馬韓、辰韓、弁韓のことを三韓と呼ぶ学説も提唱されているそうだ。 が、まあ今回は推古天皇の時代の日本の話なので、唐代と時代も合うし、日本書紀に則って高句麗・百済・新羅ということにしておこう。 とにかくそいつらが8000の軍勢で日本に攻め込んできた。 そのリーダーは「鉄人」とか「鉄大人」と言い、全身を鉄の鎧でかため、正体不明だったそうだ。人を殺して食ったりもしたらしい。今風に言うと完全に「鎧の巨人」だな。でその巨人がツクシ区(九州北部)を襲い、突破された。 これを迎え討つように命じられたのが、伊予国(愛媛県)の小千益躬(おちのますみ)という人だったが、普通に当たってもかなわない。彼は大山祗神(三嶋大明神)に必勝祈願を行ったところ、「足の裏が弱点だ」との神宣を得た。 しかしまあ、「足の裏を射よ」と言われても、普通は無理。ゲームじゃあるまいし。 そこで、小千益躬(おちのますみ)は、九州区を突破した三韓軍団を迎えに出た。「ここから先、京都まではこの私めがご案内いたします、旦那、へへへ」という作戦である。こうしてまんまととりいった小千益躬(おちのますみ)は、鉄人軍団を先導して明石の浜へやってくる。 鉄人は明石の浜の景色に見入って休もうとするのが、その時!突然カミナリが。驚いた鉄人は落馬をしてしまい(驚いたのは鉄人ではなく馬かもしれないけど)、足の裏を見せてしまう。 小千益躬(おちのますみ)はこの機を逃さず矢で足の裏を射て鉄人を仕留めた。リーダーを失った三韓軍は崩壊した。この時鉄人を射抜いた矢のことは「鬼ざしの矢」と呼ばれたという。 |
|
|
|
|
|
その鉄人を討ち取った明石の浜というのがこの神社のある場所で、小千益躬(おちのますみ)が神社を建立した。小千はこの手柄で伊予の国造に任じられたという。 もとは「稲妻神社」といい、大山祇神を祀ったが、「稲妻」が「稲爪」に転訛したのだという。 |
|
|
| |
|
小千益躬(おちのますみ)はのちに「越智」と名字を変えた。伊予国の河野氏はその子孫だというが、そのことを伝える『予章記』というのが、この鉄人伝承を伝えている。 記紀にはこの鉄人に関する記述はないため、『予章記』の記述は「謎の伝説」扱いされている。 | |
一般的な「史実」としては次のようなことがわかっている。
581年 中国で隋が成立、朝鮮遠征を行うが失敗。
593年 推古天皇が即位
628年 中国で唐が成立 同年 推古天皇の退位
646年 大化の改新
660年 唐が朝鮮遠征、百済が日本へ救援要請
663年 日本が出兵し、唐・新羅VS百済・日本のあいだに白村江の戦いが起こる
672年 壬申の乱
河野氏の開祖として知られている越智氏は、白村江の戦いに伊予水軍を率いて参加し、武功をあげた。このとき唐の娘を嫁にして生まれた子が越智玉澄(おちたますみ)といい、玉澄はのちに伊予国(いまの愛媛県松山市)に住み、河野と名を改めた。
『予章記』の通り、推古天皇の時代(593-628)にこれが起きたとすると、白村江の戦いよりも50年ほど早い時期ということになる。小千氏は南越に遠縁があり、これにちなんで越智と名を変えたそうだ。
おちのますみ 小千益躬
おちたますみ 越智玉澄
うーん
小千益躬の子に小千武男というのがあり、彼は父である小千益躬を祀るために「越智神社」を建立したそうだ。越智神社はのちに「大蔵八幡神社」と改めており、稲爪神社から500mほど東の大蔵八幡町にある。
ただし、こうした「社伝」側の侵略者を討ったサンダーボルト起源説とは違う説もある。『角川地名辞典』などでは、稲爪はもともと「稲積」のことで、古代の屯倉が置かれていたことに依るという。これは地名を「大蔵谷」(『源平盛衰記』などの表記)=「大倉谷」(『増鏡』などの表記)ということとも符号する。
また、さらなる異説として、「大蔵」は「大闇」のことで、当地のクスノキの巨木のせいで光が遮られていたことに由来する、というものもある。『釈日本紀』や『播磨国風土記(逸文)』は、当地のクスノキの大木で船が作られ、仁徳天皇に飲料水を届けるために利用されていた、と伝える。
![]()
国道2号線(山陽道)に面している。


ただし、立派な山門は裏手にある。
いまの国道2号線は後世の新ルートなんだそうで、
もともとの「旧山陽道」は神社の南側を走っているのだ。
本来はこちらが正規の入り口なんだろう。

これが山門で、ここから70mほど南へいくと旧山陽道である。
 |
狛犬さん |
 |
派手 |
  |
御朱印を所望したのですが、 宮司さんが会合か何かで不在のため無理、とのことで残念でした。 腹いせにお守りをゲット。 |
このお守りにも神社の紋「折敷に角三文字![]() 」が描かれている。
」が描かれている。
この紋は伊予国の河野氏の家紋と同じである。「折敷」は外枠の八角形のことだが、これは神社で神饌に使う台を表しており、神社そのものも意味する。河野氏はもともと瀬戸内の大三島神社(大山祇神を祀る)を信仰しており、「三」は三島のことである。
河野氏はもともと「折敷に縮三文字![]() 」という家紋を使っていた。河野氏は源平期に源義経にしがたって瀬戸内海の海戦で功をあげた。鎌倉幕府が開かれるときに酒宴に招かれたが、席次が源頼朝、北条時政に次ぐ3番目の席で、折敷の上に「三」と書いた紙がおいてあった。これをみて、頼朝の許しを得て、家紋を従来の「折敷に縮三文字」から「角三文字」に変えたのだという。
」という家紋を使っていた。河野氏は源平期に源義経にしがたって瀬戸内海の海戦で功をあげた。鎌倉幕府が開かれるときに酒宴に招かれたが、席次が源頼朝、北条時政に次ぐ3番目の席で、折敷の上に「三」と書いた紙がおいてあった。これをみて、頼朝の許しを得て、家紋を従来の「折敷に縮三文字」から「角三文字」に変えたのだという。
![]()

 |
境内末社 |
 |
|
  |
【兵庫県神社庁データ】
| 名称 | 稲爪神社 | No |
|
|
| 所在 | 明石市大蔵本町6番10号 | TEL | 078-911-3143 | |
| FAX | ||||
| 例祭日 | 本宮:10月第2月曜日(体育の日) 宵宮:その前日 |
|||
| 社格 | 旧郷社 | |||
| 祭神 | 大山祗神 | 天照大神の兄。繁栄、知恵、生命健康を授け、厄難を払う。 | ||
| 面足神 | 美を授け、物事の完成を授ける。 | |||
| 惶根神、伊和都比賣神 | 惶根神は面足神の妻。美麗と叡智を授ける。 | |||
| 交通 | ||||
| 社殿 | ||||
| 境内 | ||||
| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||
| 摂末社 | 摂社:稲爪濱恵比寿神社 末社 白玉稲荷 八将神 猿田彦神 高倉稲荷 庚申社 八大龍王神 猿田彦神 白龍神 |
|||
| 備考 | 兵庫県指定無形文化財 ・神楽獅子舞 - 宵宮で行われる大統 明石市指定無形文化財 ・牛乗りの神事 - 神社創建の縁起を伝える。 ・早口流し(囃口流し) - 宵宮で行われる宮入 |
|||
| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |
| 1578 | 天正 | 6 | 高山右近による大蔵谷攻めで焼失。北方の仮宮へ遷座。 | |||
| 1637 | 寛永 | 14 | 社殿が再興され、元の地へ戻る。 北の仮宮跡地には、明石藩主の松平光重が熊野権現を勧請し、熊野皇神社となる。 |
|||
| 1977 | 昭和 | 52 | 失火により社殿焼失 | |||
| 1979 | 54 | 社殿再建 | ||||
【参考資料】
【リンク】
*公式サイト
*古代史探訪 稲爪神社と休天神社
参拝日:2015年02月01日
追加日:2015年02月26日
修正日:2017年07月07日