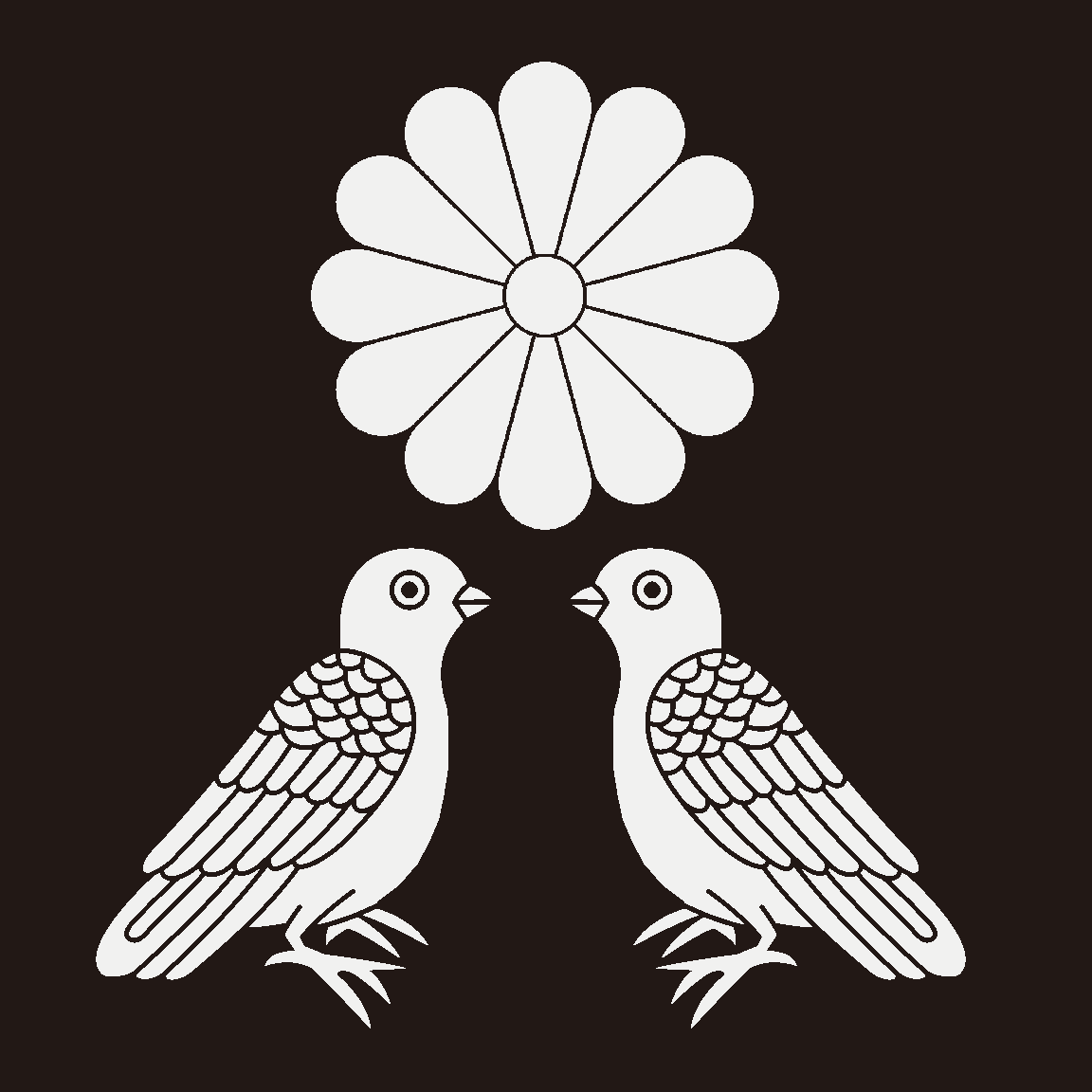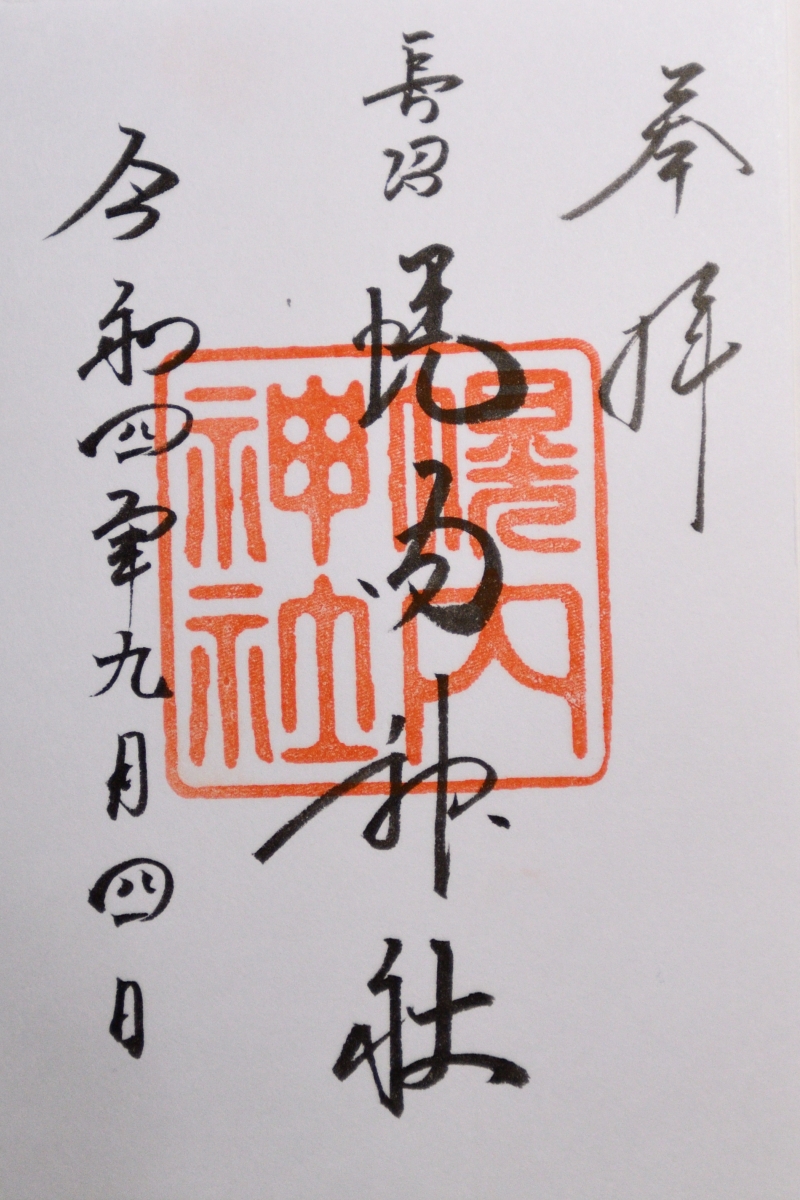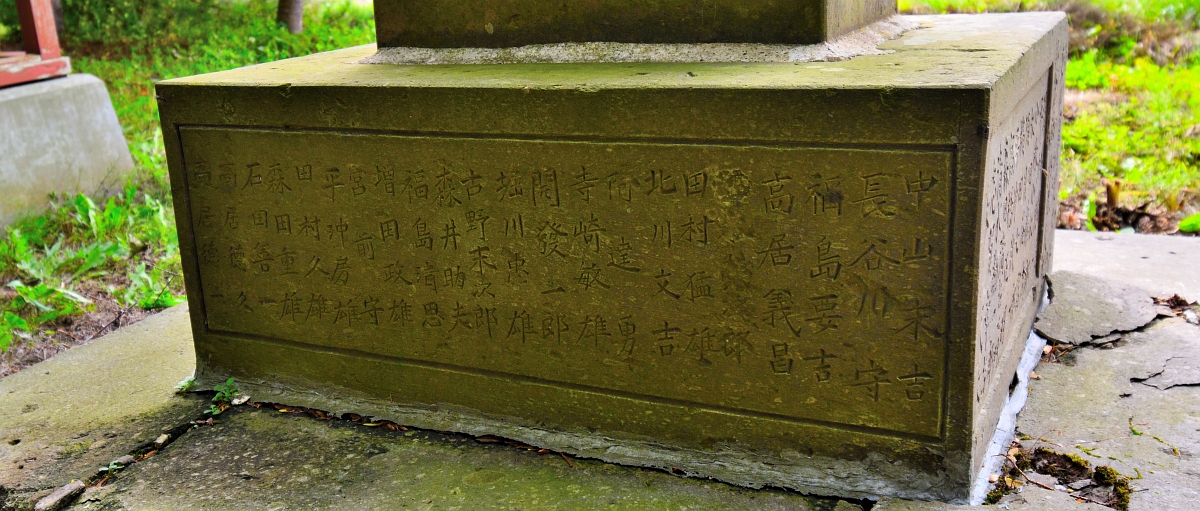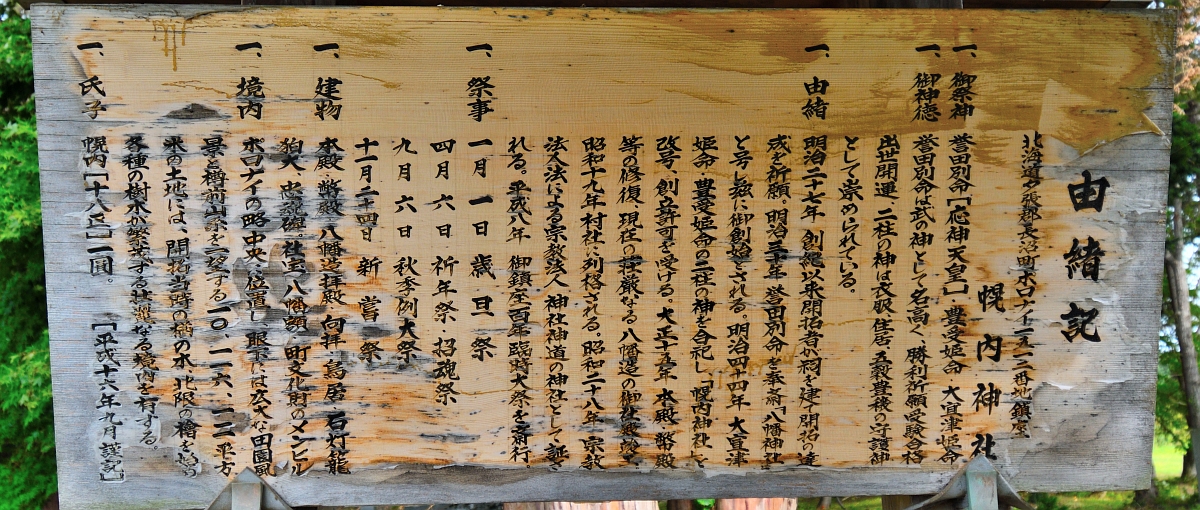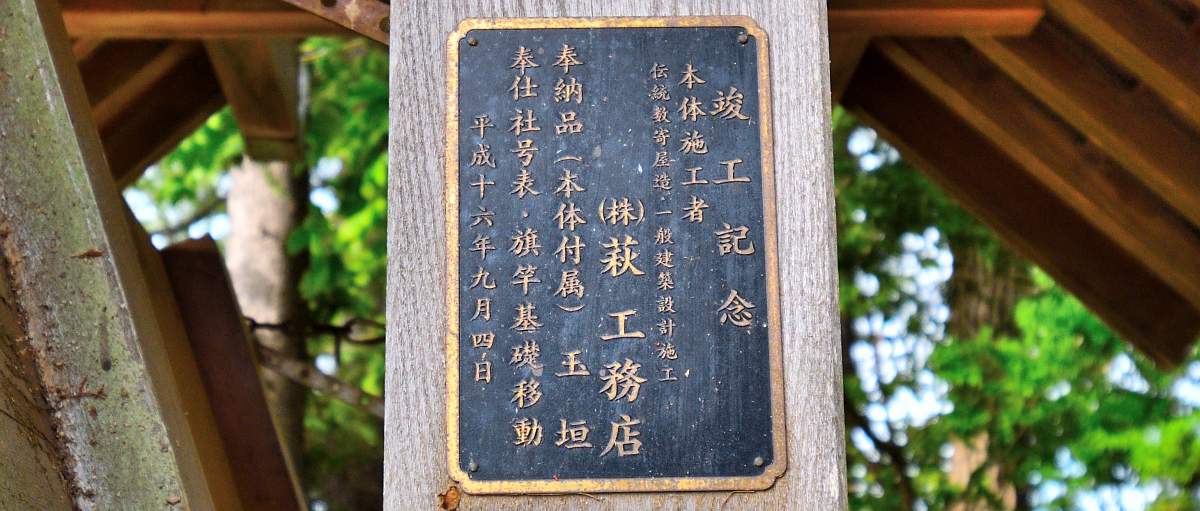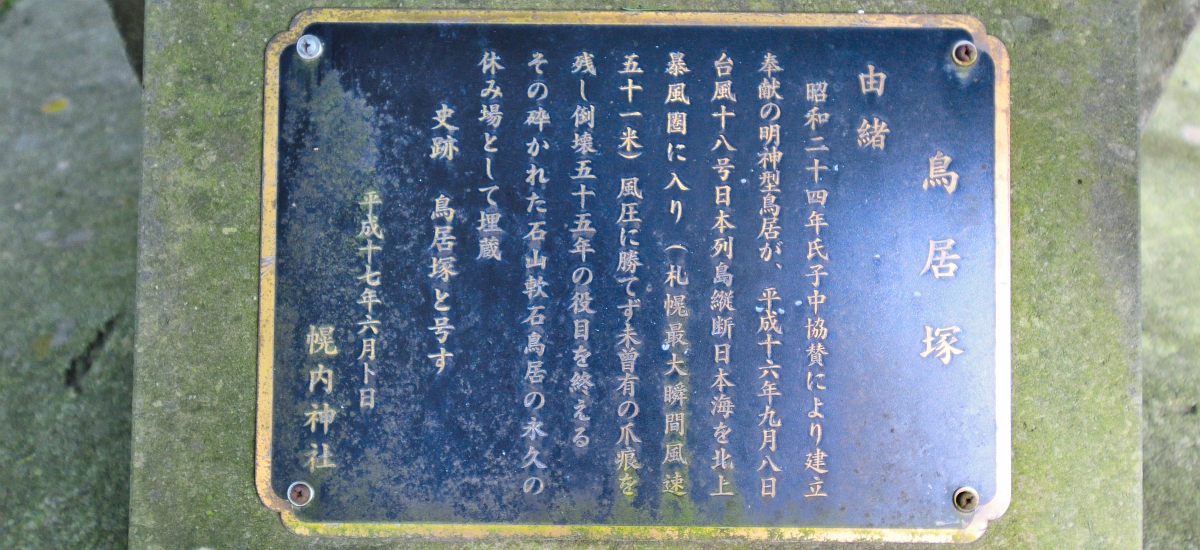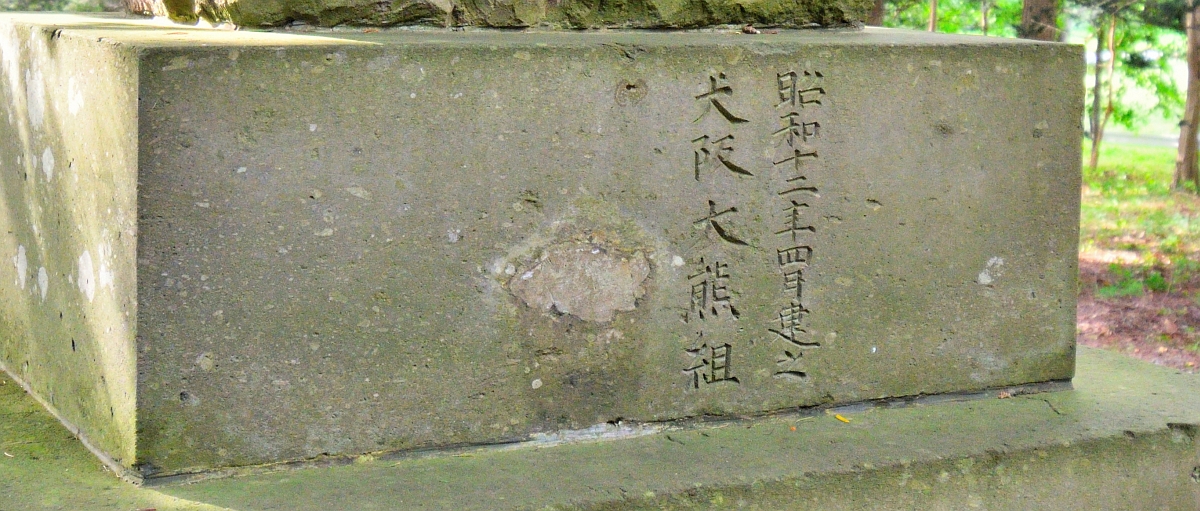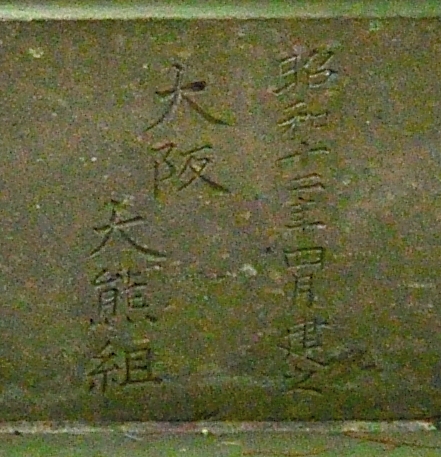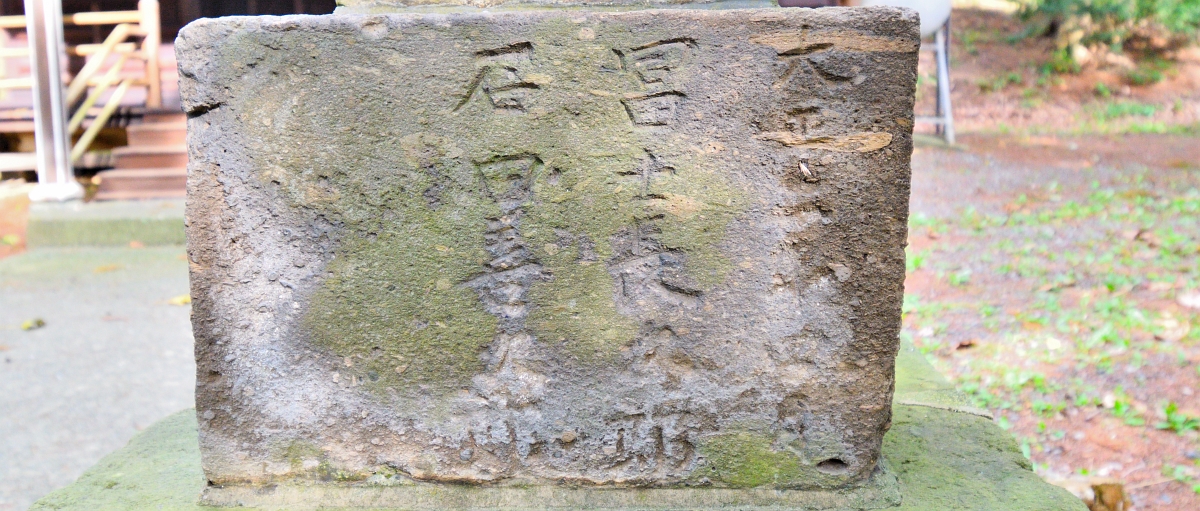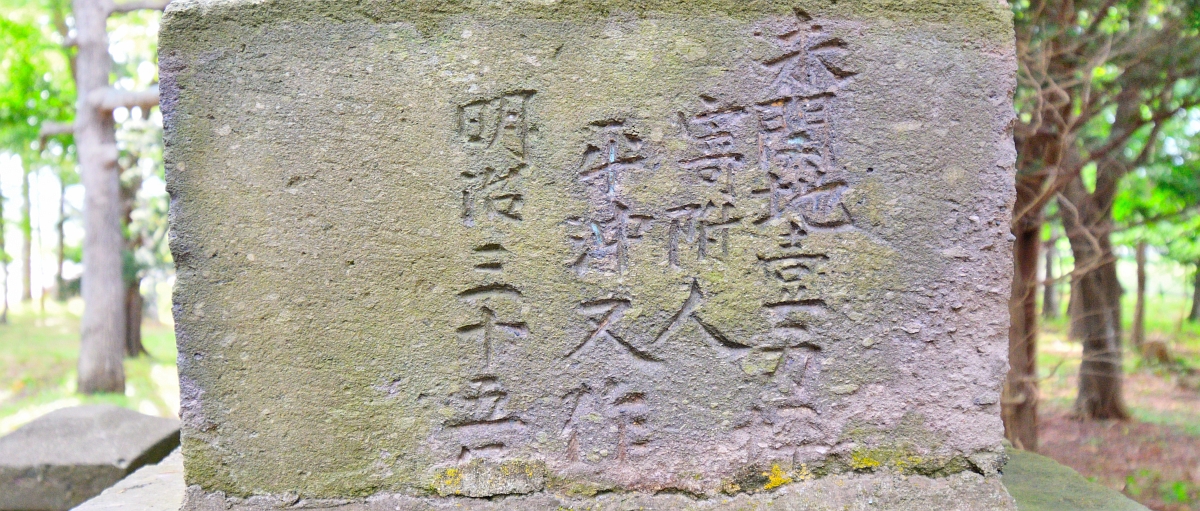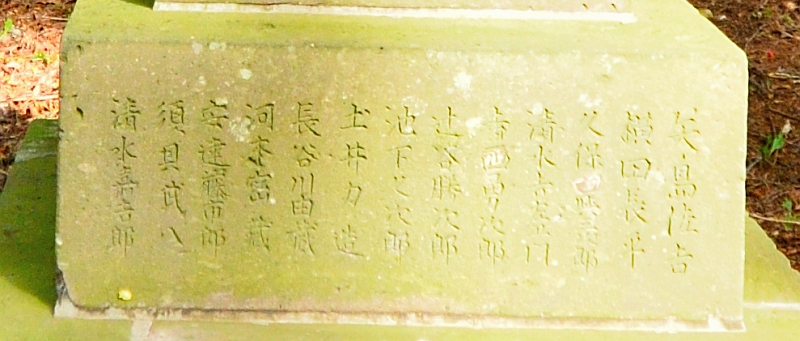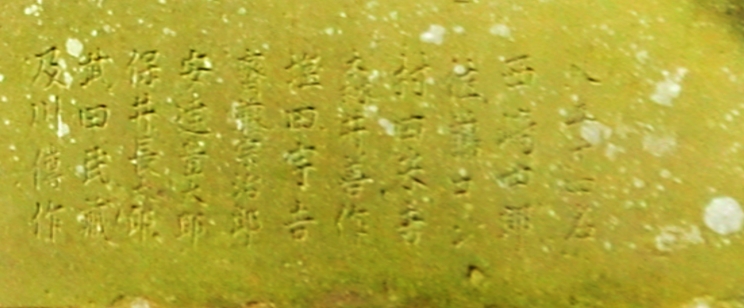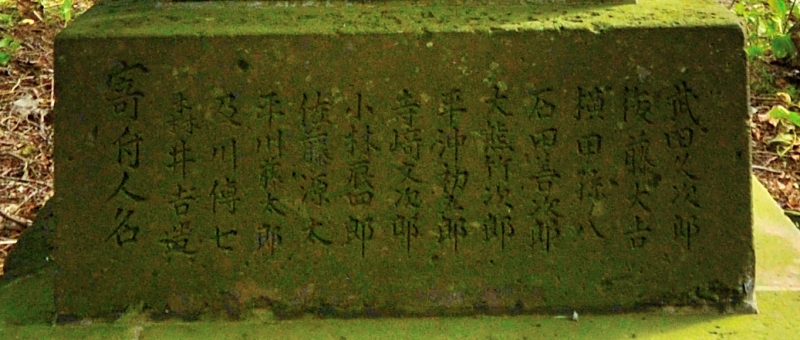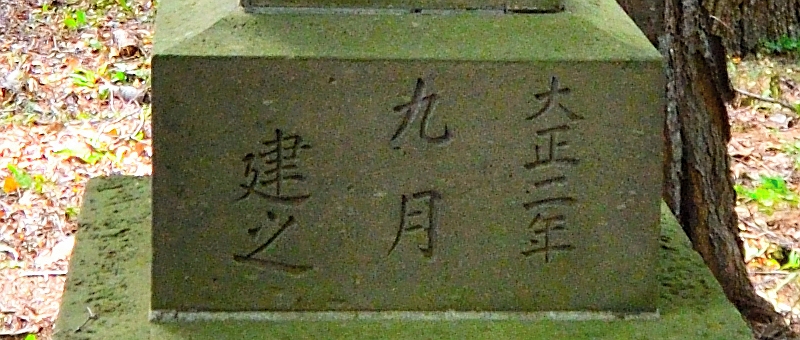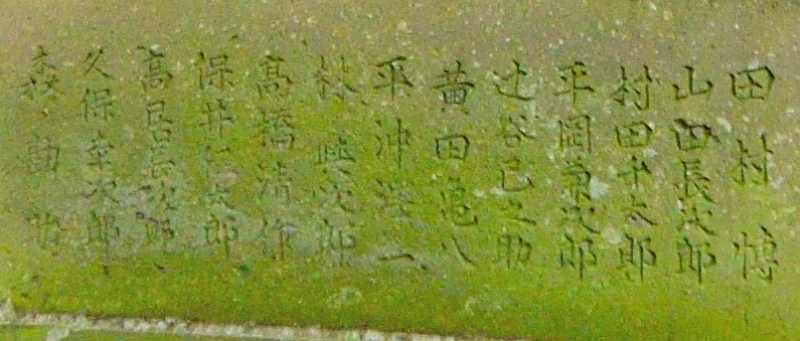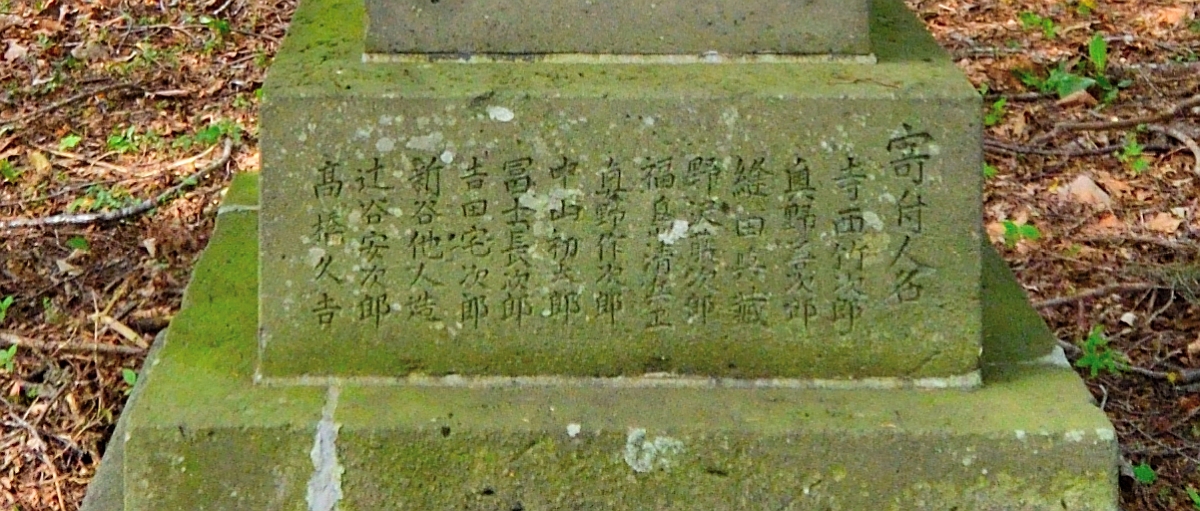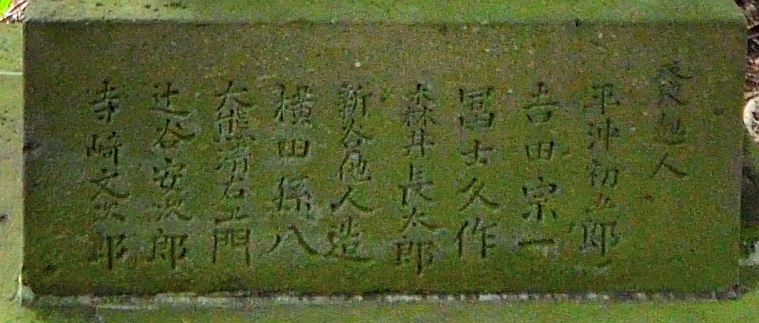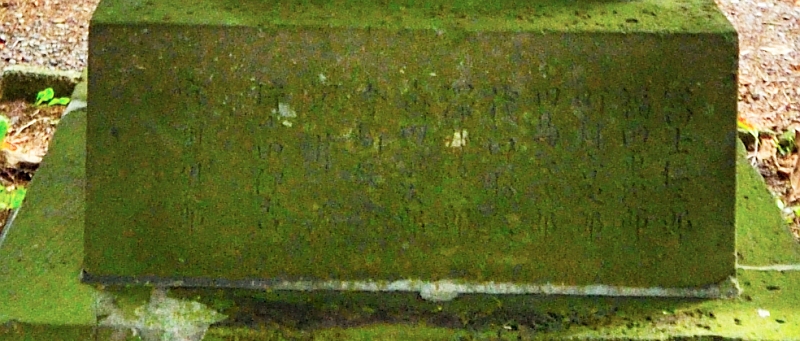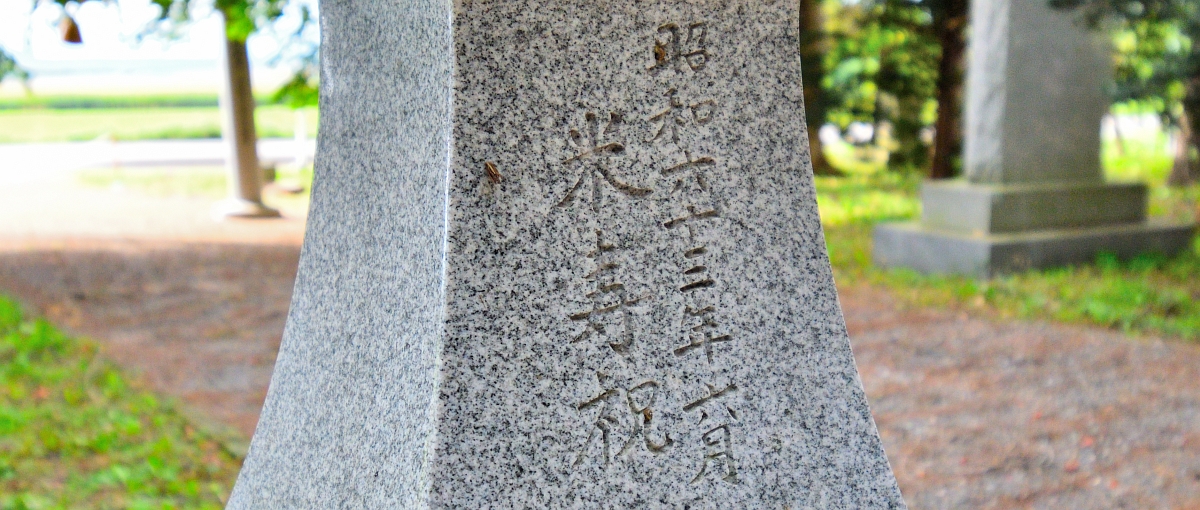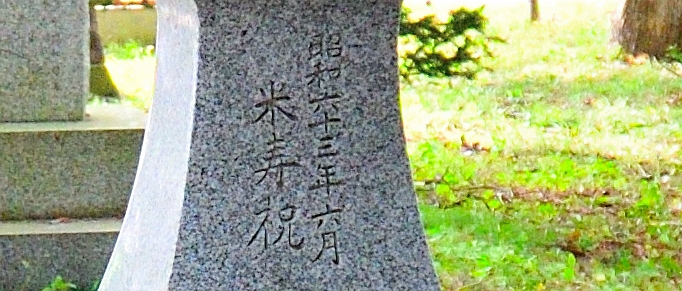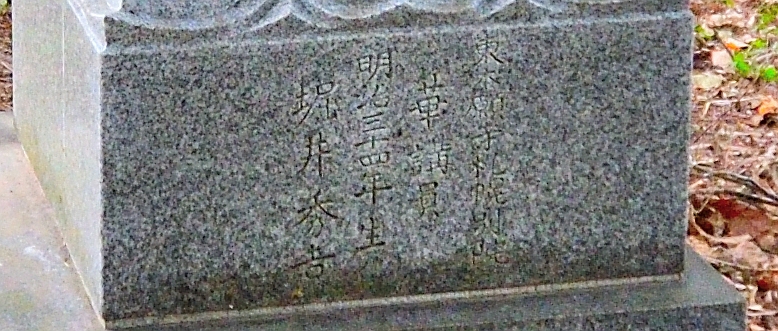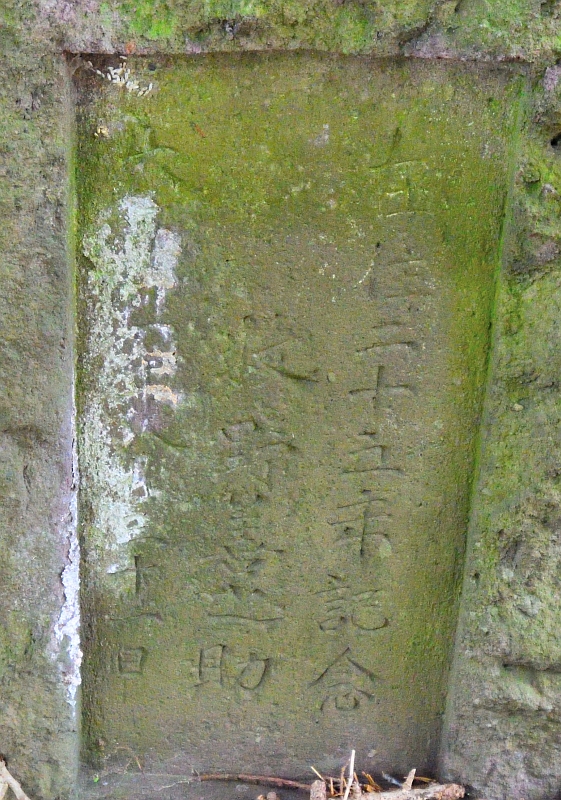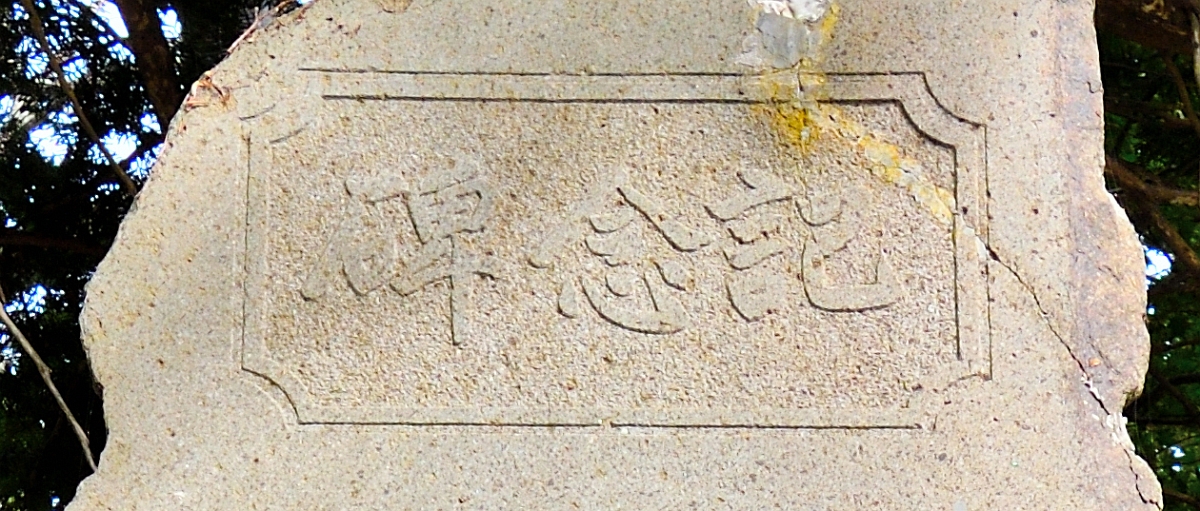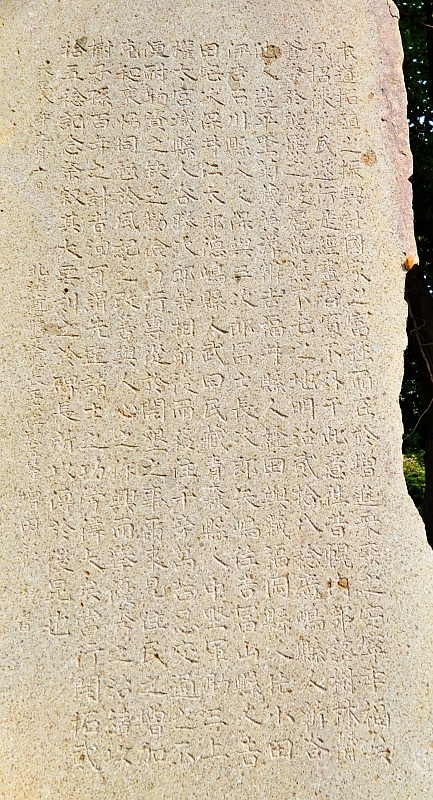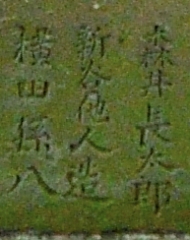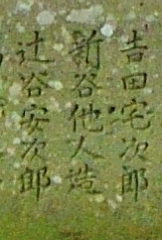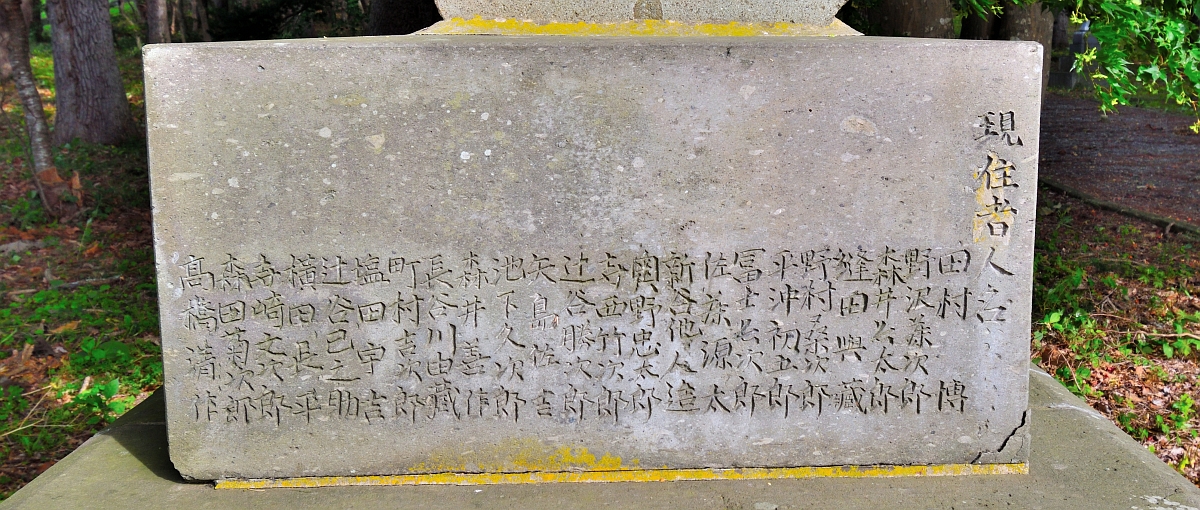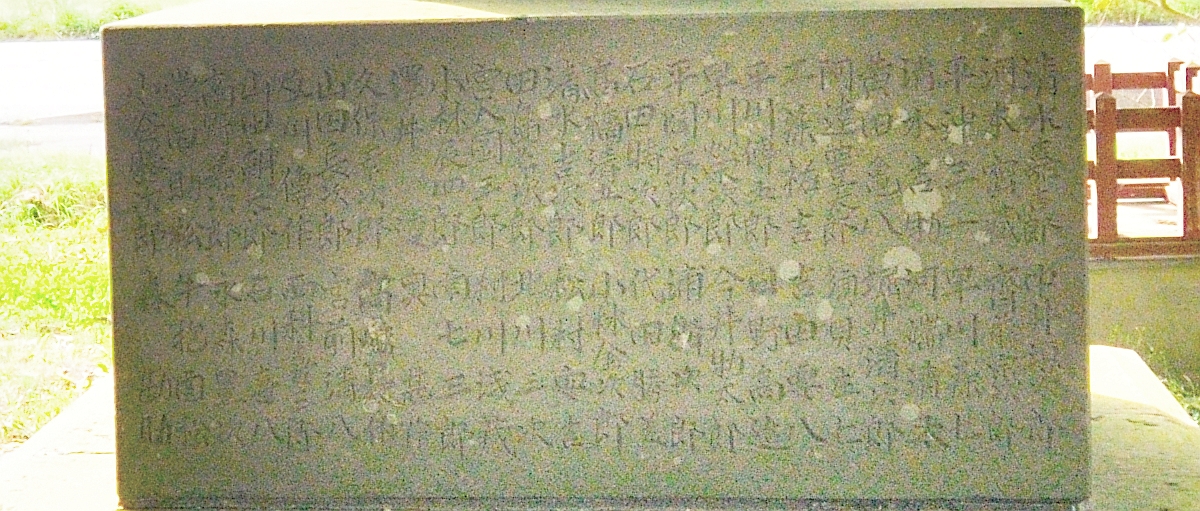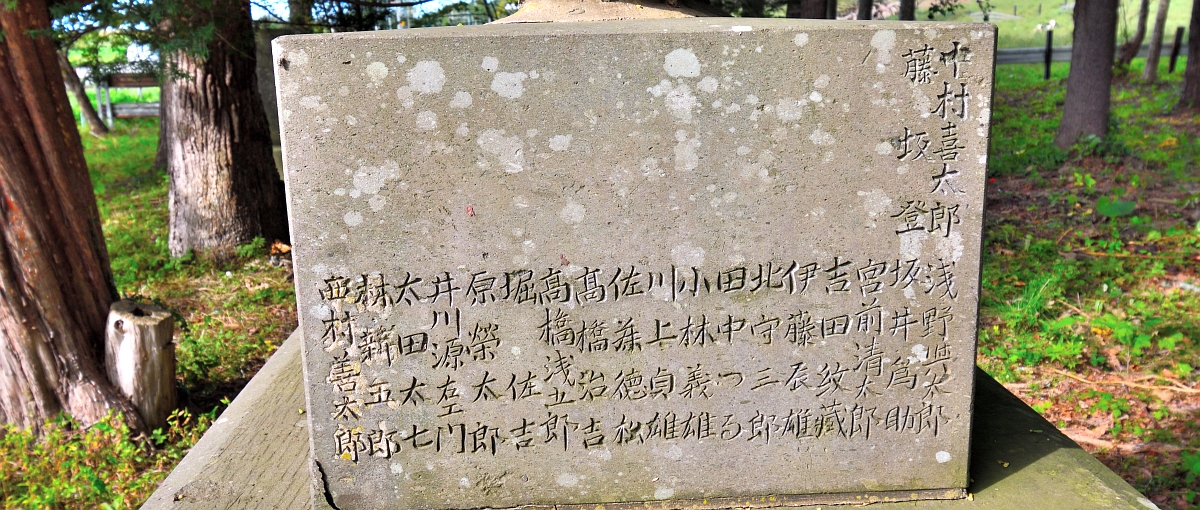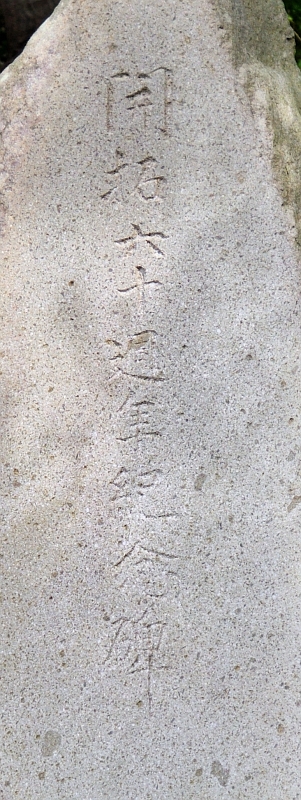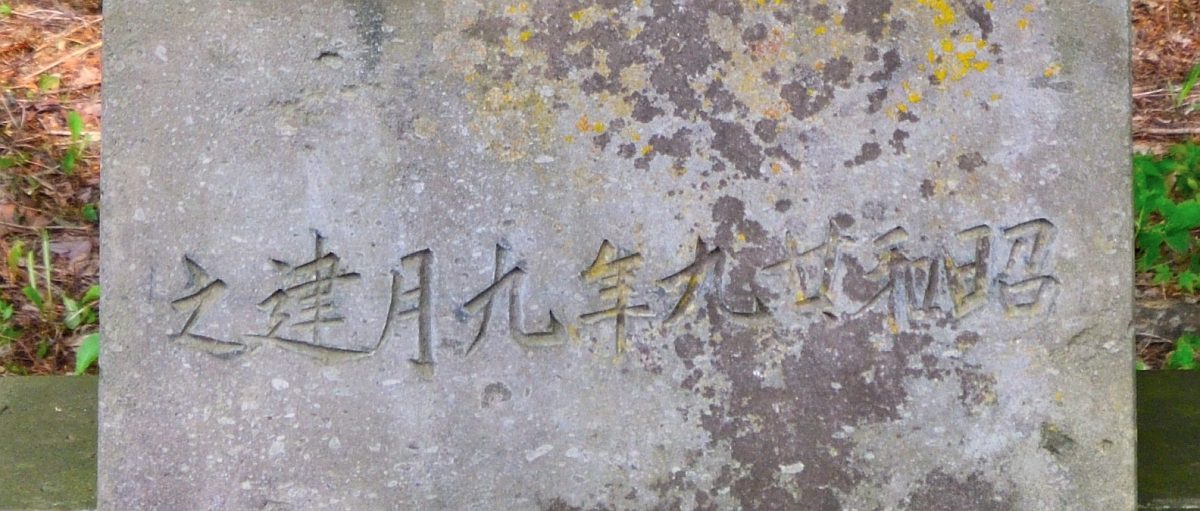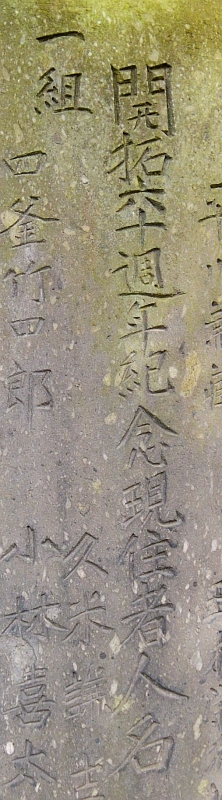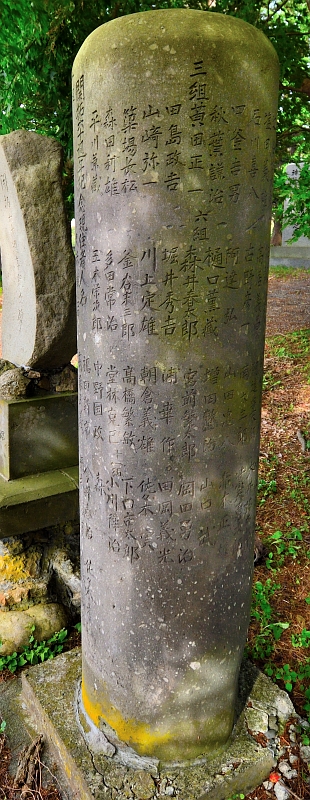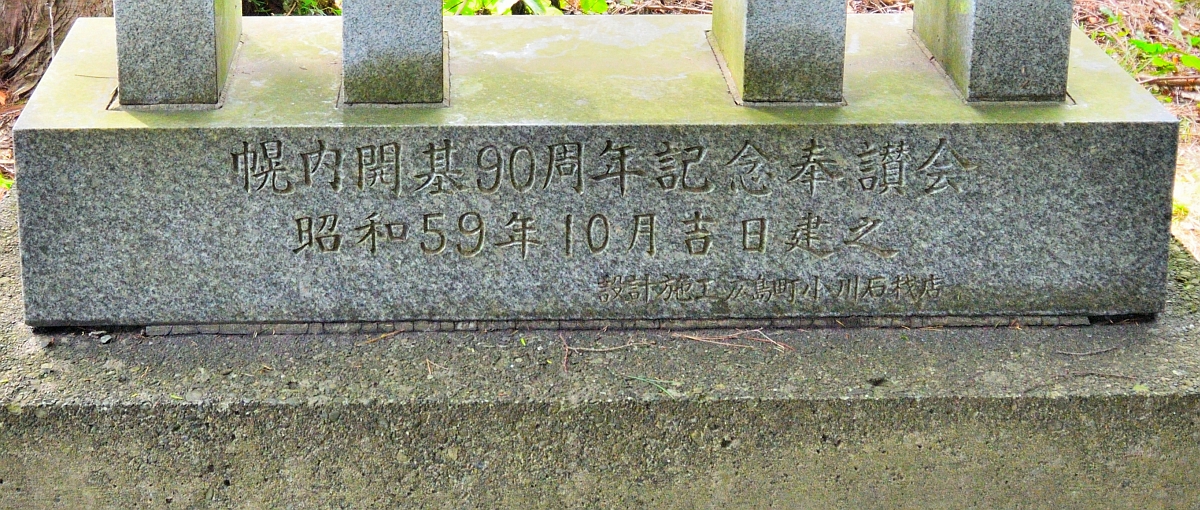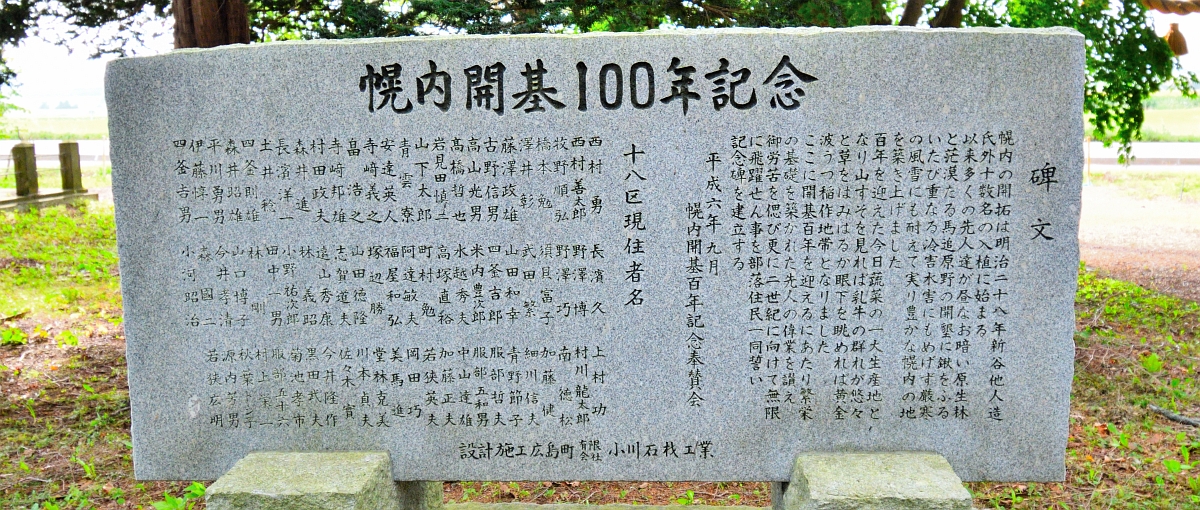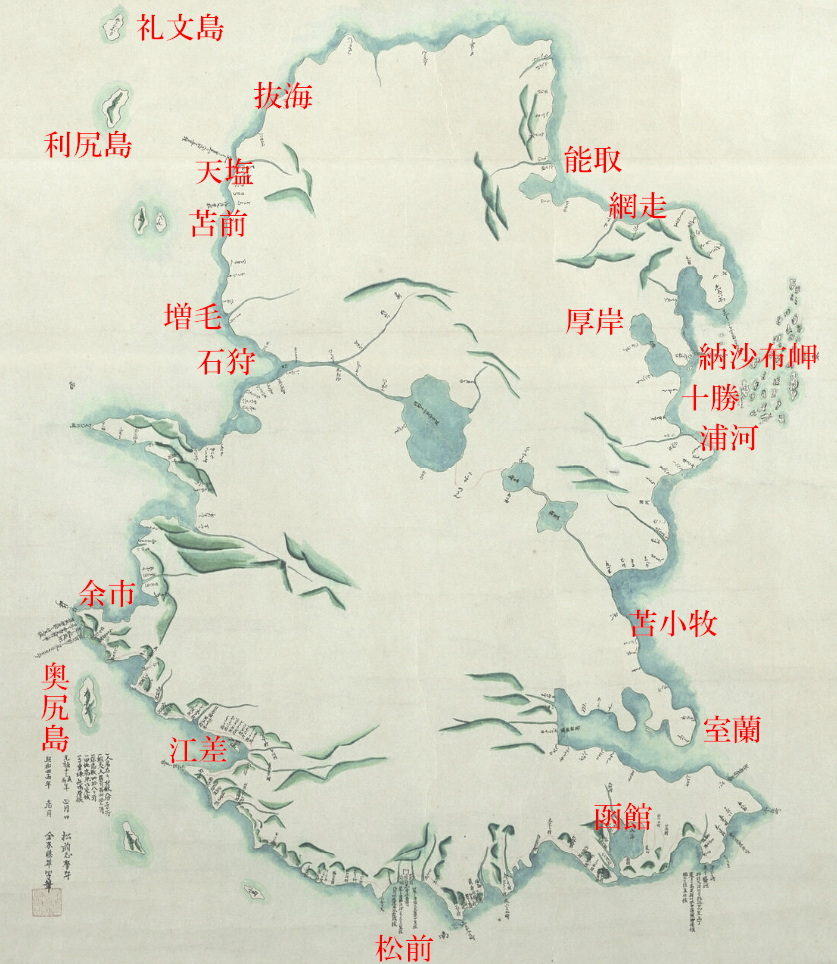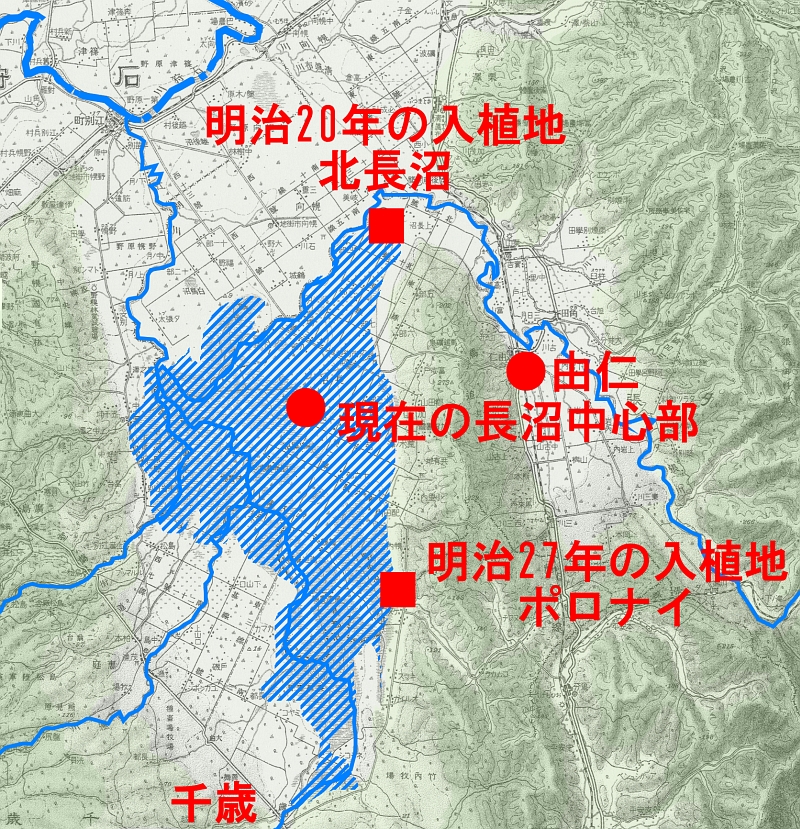| 和暦 |
西暦 |
月 |
日 |
事項 |
一般史 |
情報源 |
| 嘉永 |
6 |
年 |
(1853) |
7 |
月 |
8 |
日 |
ペリー来航 |
|
|
| 安政 |
4 |
年 |
(1857) |
|
|
|
|
松浦武四郎が、長都沼・馬追沼を渡り、対岸ポロナイに上陸 |
|
|
| 慶応 |
4 |
年 |
(1868) |
|
|
|
|
戊辰戦争 |
|
|
| 明治 |
元 |
年 |
〃 |
|
|
|
|
明治天皇即位 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
箱館戦争終結 |
|
|
| 〃 |
2 |
年 |
(1869) |
|
|
|
|
北海道開拓使設置、北海道開拓が本格化 |
|
|
| 〃 |
4 |
年 |
(1871) |
|
|
|
|
北海道神社改正(北海道内での神社行政の開始) |
|
|
| 〃 |
8 |
年 |
(1875) |
|
|
|
|
千歳の稲荷神社(主祭神豊受姫大神)が郷社に列格 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
20 |
年 |
(1887) |
|
|
|
|
長沼開基(北長沼) |
|
|
| 〃 |
22 |
年 |
(1889) |
|
|
|
|
千歳村から三川・由仁への道路(千歳道路)が開削 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
25 |
年 |
(1892) |
|
|
|
|
夕張郡由仁村の外村として「長沼村」設立 |
|
|
| 〃 |
27 |
年 |
(1894) |
7 |
月 |
25 |
日 |
日清戦争勃発 |
|
|
| 〃 |
27 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
千歳村からポロナイへの最初の入植者15名。千歳村番外地と定める。 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
ポロナイ入植者が小祠を営む(幌内神社の濫觴)
|
|
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
ポロナイ入植者が神社建立を計画 |
|
『幌内九十年史』
(旧)『長沼村史』
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
28 |
年 |
(1895) |
|
|
|
|
ポロナイ入植者たちが、この年を「ポロナイ開基元年」とすることを決める |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
長沼村に戸長役場を設置 |
|
|
| |
29 |
年 |
(1896) |
2 |
月 |
|
|
入植者が神社建立のため永続資金を募る |
|
『長沼町九十年史』
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
入植者たちにより小祠建立、「八幡神社」と号す(無願神社)(※異説あり) |
|
『幌内神社百年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
2 |
日 |
誉田別命を奉斎し、「八幡神社」と号す(※異説あり) |
|
現地由緒書
(新)『長沼村史』
『長沼町の歴史 上巻』
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
30 |
年 |
(1897) |
|
|
|
|
誉田別命を奉斎、「幌内神社創設起源」とする(※異説あり) |
|
『幌内神社百年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
初代社掌として、千歳村稲荷(千歳神社)神主の溝口五左ェ門を招聘 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
32 |
〃 |
(1899) |
2 |
月 |
|
|
神社予定地として三町十八歩(約29,811㎡)を購入 |
|
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
33 |
年 |
(1900) |
|
|
|
|
向拝柱造の外祠宮を建立。現在は社殿内に本殿として安置。 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
35 |
年 |
(1902) |
2 |
月 |
15 |
日 |
拝殿を建立、上棟式を執行。建築位置は、現在の国道に面する付近。 |
|
『幌内九十年史』
『続幌内神社史』
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
平沖又作が、土地一万坪(約33,322㎡)を寄進 |
|
『続幌内神社史』
現地石燈籠台石 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
37 |
年 |
(1904) |
|
|
|
|
日露戦争開戦 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
二〇三高地戦 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
38 |
年 |
(1905) |
頃 |
|
|
|
横田孫市らが八幡神社鳥居の社額を奉納(現在は拝殿内に保存) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
5 |
日 |
日露戦争終結 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
43 |
年 |
(1910) |
|
|
|
|
奥の院(本殿)を建立、祠宮を納める。(この奥の院は、のちに現在地へ移設。) |
|
『続幌内神社史』
『北海道神社庁誌』
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
豊受姫命、大宜津姫命を合祀(※異説あり) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
神社用地を買い増しすると共に、神社改築資金を募る |
|
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
1 |
日 |
神社の創立出願 |
|
(旧)『長沼村史』
(新)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
豊受姫命を合祀(※異説あり) |
|
現地由緒書
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
幌内神社に改称。(※異説あり) |
|
現地由緒書
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
44 |
年 |
(1911) |
5 |
月 |
18 |
日 |
創立許可を得る。(※異説あり) |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
幌内神社に改称。(※異説あり) |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
無格社に列格。(※異説あり) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
大宜津姫命を合祀(※異説あり) |
|
現地由緒書 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
社殿改築に着手 |
|
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
六寸丸型の御神鏡を御霊代として奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
平沖又作が、土地三町一畝十八歩(約29,911㎡)を寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
|
|
鈴木牧場支配人の山口若松より、土地三町四畝十五歩(約30,198㎡)を購入 |
|
『続幌内神社史』
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
社殿落成 |
|
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
45 |
年 |
(1912) |
5 |
月 |
|
|
創立許可を得る。(※異説あり) |
|
『北海道神社庁誌』
(旧)『長沼村史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
無格社に列格。(※異説あり) |
|
『北海道神社庁誌』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
幌内神社に改称。(※異説あり) |
|
(旧)『長沼村史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大正 |
2 |
年 |
(1913) |
|
|
|
|
拝殿(明治35年建立)を改築、5坪(約16.53㎡)。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
5 |
月 |
|
|
社殿の右に立石(メンヒル)を陳列保存。 |
|
『幌内九十年史』
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
石燈籠一対(㉑㉒)奉納、現在社殿前に位置。 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』
現地石燈籠台石 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
石燈籠一対(⑰⑱)奉納、現在表参道中間に位置。 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』
現地石燈籠台石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
3 |
年 |
(1914) |
|
|
|
|
第一次世界大戦勃発 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
7 |
年 |
(1918) |
11 |
月 |
11 |
日 |
第一次世界大戦終結 |
|
|
| 〃 |
8 |
年 |
(1919) |
9 |
月 |
1 |
日 |
幌内開拓二十五記念碑を建立 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
忠魂碑を建立 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』
現地忠魂碑碑文 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
10 |
年 |
(1921) |
|
|
|
|
境内地に隣接する土地五畝歩(約496㎡)が山城与三吉から寄進される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
11 |
年 |
(1922) |
8 |
月 |
31 |
日 |
手水鉢一基(㉓)を奉納(長沼在住二十五年記念) 。現在社殿前に位置。 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』
現地手水鉢 |
| 〃 |
12 |
年 |
(1923) |
4 |
月 |
|
|
手水鉢一基(⑯)を奉納(81歳長寿記念)。現在参道中央に位置。 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
14 |
年 |
(1925) |
10 |
月 |
5 |
日 |
神社敷地寄附の功労者として、平沖又作が北海道神宮から表彰を受ける |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
15 |
年 |
(1926) |
4 |
月 |
7 |
日 |
神殿・幣殿・拝殿改築(現存社殿)の上棟式を斎行 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
幌内神社の神職担当が千歳神社から長沼神社に移管 |
|
『続幌内神社史』 |
| 昭和 |
2 |
年 |
(1927) |
5 |
月 |
|
|
表参道社殿前の階段を改修、コンクリート製となる |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
6 |
年 |
(1931) |
|
|
|
|
満州事変 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
11 |
年 |
(1936) |
2 |
月 |
26 |
日 |
二・二六事件 |
|
|
| 〃 |
12 |
年 |
(1937) |
4 |
月 |
|
|
狛犬一対(⑲⑳)を奉納。参道石段下に位置。 |
|
『続幌内神社史』
『幌内九十年史』
現地狛犬台座 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
7 |
日 |
支那事変勃発 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
14 |
年 |
(1939) |
9 |
月 |
1 |
日 |
第二次世界大戦勃発(ドイツがポーランドへ侵攻) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
16 |
年 |
(1941) |
|
|
|
|
御神鏡(丸寸丸型・雲台付クローム鏡)奉納。支那事変からの無事帰還記念として。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
7 |
日 |
社号標建立。満州事変出征記念として。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
8 |
日 |
日米開戦(真珠湾攻撃) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
18 |
年 |
(1943) |
7 |
月 |
1 |
日 |
大鳥居の両側に由緒記・制札を建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
19 |
年 |
(1944) |
|
|
|
|
狩衣・白衣・御稚児着5着を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
20 |
日 |
村社に列格 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
10 |
月 |
|
|
神饌幣帛料供進神社に指定 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
秋祭りを村社昇格奉告祭として執行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
20 |
年 |
(1945) |
5 |
月 |
|
|
ドイツ降伏 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
15 |
日 |
日本降伏 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
GHQの神道指令(国家神道・社格の廃止など) |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
奉納されていた創作額(古銭で鳥居を象ったもの)が盗難 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
21 |
年 |
(1946) |
|
|
|
|
神社本庁設立 |
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
宗教法人法に拠る宗教法人となる(※) |
|
『長沼町の歴史 上巻』
『北海道神社庁誌』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
24 |
年 |
(1949) |
|
|
|
|
大鳥居(石造・明神型)建立(現存せず) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
社殿柾葺屋根の葺き替え |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
26 |
年 |
(1951) |
|
|
|
|
自作農創出特別措置法により、社有地のおよそ3分の2を供出、境内敷地が10,763㎡となる |
|
『北海道神社庁誌』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
27 |
年 |
(1952) |
3 |
月 |
4 |
日 |
十勝沖地震。大鳥居に亀裂 |
|
|
| 〃 |
28 |
年 |
(1953) |
3 |
月 |
|
|
宗教法人法に基づく宗教法人と認証、登記を実施。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
神社本庁に所属 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
29 |
年 |
(1954) |
9 |
月 |
|
|
幌内開基60周年記念碑(⑧⑨)を建立 |
|
『続幌内神社史』
現地石碑碑文 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
神殿の幕・祝詞屋の幕を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
33 |
年 |
(1958) |
|
|
|
|
社殿柾葺きをトタン張りに葺き替え |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
37 |
年 |
(1962) |
|
|
|
|
本染め幟(祭典用、大小各2旒)を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
38 |
年 |
(1963) |
|
|
|
|
札幌神社を北海道神宮へ昇格させるための協力委員に任命、協賛金を支出 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
39 |
年 |
(1964) |
|
|
|
|
開基70周年記念碑建立のため、台石を馬追山から搬出 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
幌内開基70周年記念碑(⑤)を建立 |
北海道冷害 |
『続幌内神社史』
現地石碑碑文 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
祭典用幟旗旗竿固定用の鉄製アングルを設置 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
42 |
年 |
(1967) |
|
|
|
|
神苑大石を奉納(田島家・移住記念) |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
45 |
年 |
(1970) |
|
|
|
|
隣接する長濱牧場の湧水を分水し、拝殿前の手水所と地区会館へ水道管を敷設 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
46 |
年 |
(1971) |
4 |
月 |
|
|
幌内長楽会により境内にライラック、八重桜、ナナカマドを植樹 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
47 |
年 |
(1972) |
|
|
|
|
拝殿向拝所の鈴及び鈴の緒が奉納される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
48 |
年 |
(1973) |
|
|
|
|
拝殿用の座布団40枚が寄進される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
49 |
年 |
(1974) |
|
|
|
|
板張り床の拝殿用に、畳24枚が寄進される。これにより暖かくなったという |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
|
|
幌内開基80周年(⑩)の石碑を建立 |
|
『続幌内神社史』
現地石碑碑文 |
| 〃 |
51 |
年 |
(1976) |
1 |
月 |
|
|
元旦祭用の神饌御神酒一斗(18リットル)を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
20 |
日 |
社殿大改修に先立ち、遷座祭を奉斎し、御霊代を長沼神社へ遷座 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
|
|
社殿(祀宮・拝殿)の改修・境内整備(御神紋入天幕・外幕・内幕、電話線整備、参道砂利敷き等)完了。現在の社殿。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
2 |
日 |
社殿落成奉告祭 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
日 |
正遷座祭を斎行し、御霊代を戻す |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
祀宮の前飾り猫足六角型吊燈籠一対奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
52 |
年 |
(1977) |
|
|
|
|
吊燈籠(銅製・春日型)が奉納される(金婚式記念) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
御神紋入社名旗が奉納される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
拝殿暖房用の煙突が寄進される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
吊燈籠と社名旗の奉納者それぞれに感謝状 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
53 |
年 |
(1978) |
|
|
|
|
社殿内調度品として金幣が奉納される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
金幣の奉納者に感謝状 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
社殿に照明用電気工事を実施 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
54 |
年 |
(1979) |
|
|
|
|
拝殿内に錦旗(日月旗・錦地五色瑞雲柄織・両面仕立・金玉・千段巻竿・枠台・黒塗・本金鍍金錺金具付)が奉納される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
錦旗の奉納社に感謝状 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
55 |
年 |
(1980) |
|
|
|
|
祭典用の大幟旗(本染大幟旗)を一対(二流)作成 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
56 |
年 |
(1981) |
|
|
|
|
祭典用の大幟旗一対及び固定用の台を作成 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
大幟旗の製作者に感謝状 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
57 |
年 |
(1982) |
|
|
|
|
昭和27年(1952)の十勝沖地震で損傷(亀裂)していた大鳥居の大修理工事を実施。損傷部を鉄板で囲む補強。 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
表参道の両側に縁石を敷設 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
24 |
日 |
隣地との境界確認を実施 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
鳥居修理の実施者に感謝状 |
|
|
| 〃 |
58 |
年 |
(1983) |
|
|
|
|
前年の境界確認に基づき、神社用地が隣地へ越境していた部分(149㎡)を、隣地所有者から神社へ寄附 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
重要書類保管用の耐火金庫1基が寄贈される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
土地の寄附者や物品の寄贈者にそれぞれ感謝状 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
59 |
年 |
(1984) |
|
|
|
|
由緒記・制札を補修 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
本堂向拝所の柱及び燈籠一対の修繕 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
60 |
年 |
(1985) |
|
|
|
|
大鳥居の社名額の大修理 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
幟旗旗竿の固定台および忠魂碑玉垣の鉄部を塗装 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
63 |
年 |
(1988) |
6 |
月 |
|
|
石燈籠一対(⑭⑮)が奉納される(米寿記念) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
創作額(硬貨で作った明神鳥居)を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 平成 |
元 |
年 |
(1989) |
|
|
|
|
拝殿向拝所の本坪鈴を新調 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
2 |
年 |
(1990) |
|
|
|
|
注連縄2連を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
3 |
年 |
(1991) |
|
|
|
|
神社社屋に損害保険をかける |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
6 |
年 |
(1994) |
|
|
|
|
座敷用の箒2本が寄進される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
4 |
日 |
幌内開基100周年記念碑(⑬)を建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
8 |
年 |
(1996) |
|
|
|
|
祠宮(本殿)前に座礼用三段物案(神饌を供える卓)を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
祠宮(本殿)前内陣に雪洞朱塗菊座台付置燈籠一対を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
祠宮(本殿)用紫本染御神紋・社紋入白抜天竺木綿織神前内幕幕房付1張を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
社殿前庭両側に五色吹流し2播奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
祠宮(本殿)の屋根の千木を交換 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
創建100年記念碑(⑫)を建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
8 |
日 |
御鎮座百年臨時大祭を奉斎 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
10 |
年 |
(1998) |
|
|
|
|
祭事用大幟旗の旗竿一対・竿固定台付を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
昭和57年実施の大鳥居の補強部に亀裂を発見し、再補強 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
11 |
年 |
(1999) |
1 |
月 |
20 |
日 |
宗教法人幌内神社規則を再策定 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
大鳥居の大注連縄(前垂鼓胴大根型麻色・合成繊維製)1連を寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
篝火台(足付鉄製黒色耐火塗料使用火袋二尺五寸)1台製作 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
物置(イナバ金属製MBX30)1棟・基礎工事 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
拝殿内の水道工事(流し周り整備)・浸透枡・壁鏡1面 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
拝殿内暖房用灯油ストーブ・灯油タンク整備 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
桜苗木を補植 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
参道の照明設置用ポール12本を製作 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
12 |
年 |
(2000) |
|
|
|
|
創作額(昭和63年奉納)の腐食のため改修 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
社屋周辺の防腐剤塗装、拝殿外灯工事 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
13 |
年 |
(2001) |
|
|
|
|
由緒記・制札2棟の屋根トタンの葺替 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
拝殿床下基礎地束・石段欄干の補修・防腐剤塗装 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
本殿正面虹梁(化粧梁)に朱漆塗装 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
拝殿内装工事(壁代・朽木摺布筋片面仕様茶摺テトロンタフタ袷仕立)、障屏具 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
大鳥居の社額の補修 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
境内樹木の損傷部の治療 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
何者かに本殿の扉を破損される |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
防犯灯の整備 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
殿内調度品の新調(緋毛氈・門帳・御簾) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
14 |
年 |
(2002) |
|
|
|
|
神社沿革および歴代神官・役員芳名を扁額とする |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
祠宮(本殿)の大床の破損修復・内装白布張替え工事を行う |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
大鳥居前と忠魂碑前に防犯用の鎖を設置。ほか防犯灯改装など防犯工事を施す |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
15 |
年 |
(2003) |
|
|
|
|
おみくじ用の箱・絵馬掛け台を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
2 |
月 |
|
|
神社規則を一部改定 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
|
|
創建以来の神器・石碑を撮影したパネルを奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
裏参道の本殿南側に砂利敷駐車場を整備(ダンプ10台分の砂利など資材は寄進による) |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
|
|
座布団10枚・座布団カバー40枚を新調 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
雅楽演奏用のミニコンポ・CDを購入、設置用の棚を製作奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
暖房のためサーキュレーター2台を購入 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
祠宮(本殿)前の六角吊り燈籠一対を幣殿へ移設 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
初詣用にコンクリート階段に敷く絨毯マットを寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
16 |
年 |
(2004) |
1 |
月 |
1 |
日 |
祭礼用斎衣(三紋社紋・衿社名入り交織白地有紋紐付小忌衣)6着寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
衣装収納具を製作 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
|
|
前面道路(国道337号)拡幅のため、境内地497.88㎡の売却と、当該部の立木・工作物の補償について、国(札幌開発建設部)と契約締結 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
3 |
日 |
道路用地内の立木・工作物の伐採・移転工事のため御霊移しの儀を執行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
5 |
日 |
旗竿基礎工事・社号標移設工事 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
日 |
立木伐採工事 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
3 |
日 |
旗竿移設、由緒記・制札の新築建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
日 |
秋の大祭・幌内開基110年奉告祭、境内工作物の清め・入魂奉告祭を執行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
日 |
台風18号により大鳥居倒壊、境内立木折損 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
18 |
日 |
神社役員会を開催し鳥居再建を検討 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
10 |
月 |
2 |
日 |
台風に因る倒木を撤去、神社総代会で鳥居再建案を決議 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
23 |
日 |
新嘗祭 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
24 |
日 |
新嘗祭奉斎をテレビ局(札幌テレビ放送(STV))が取材。翌年5月に放送 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
作業手袋1ダースを寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
倒壊した大鳥居の社額を本殿向拝所正面に移設 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
長沼町十八区(幌内地区)総会で鳥居再建の支援を要請、150万円の資金援助を得る |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
17 |
年 |
(2005) |
1 |
月 |
1 |
日 |
元旦祭 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
公有地の測量・所有権移転手続 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
日 |
タオル地手拭い15枚を寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
5 |
月 |
|
日 |
桜・松・オンコの苗木を寄進 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
25 |
日 |
新鳥居建立の地鎮祭執行、由緒記・制札に玉垣奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
28 |
日 |
倒壊した旧鳥居を「鳥居塚」とするため基礎工事を実施 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
月 |
4 |
日 |
新鳥居が到着、建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
16 |
日 |
新鳥居の貫・楔接合部にシリコンコーキングを施工 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
|
|
鳥居塚を建立 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
3 |
日 |
表参道の縁石補修資材の寄進・補修工事を実施 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
新鳥居に新調の注連縄を張る |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
17 |
日 |
新鳥居と鳥居塚の銘板を設置 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
24 |
日 |
新鳥居と鳥居塚の入魂式を執行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
10 |
月 |
|
|
前面道路拡幅部に歩道新設工事 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
|
|
本殿大何処に擬宝珠勾欄付玉垣を新設 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
18 |
年 |
(2006) |
3 |
月 |
|
|
『幌内神社史』編纂 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
拝殿扉の補修・鈴緒を設置 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
鈴緒(三色染麻三本撚六角桐枠)を奉納 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
|
|
セキュリティ装置・鍵を破壊され、賽銭箱を荒らされる |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
23 |
日 |
賽銭箱に神紋社紋の彫刻を実施 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
6 |
日 |
秋季例大祭を御創祀110年記念大祭として執行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
22 |
日 |
『新幌内神社史』刊行 |
|
『続幌内神社史』 |
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
|