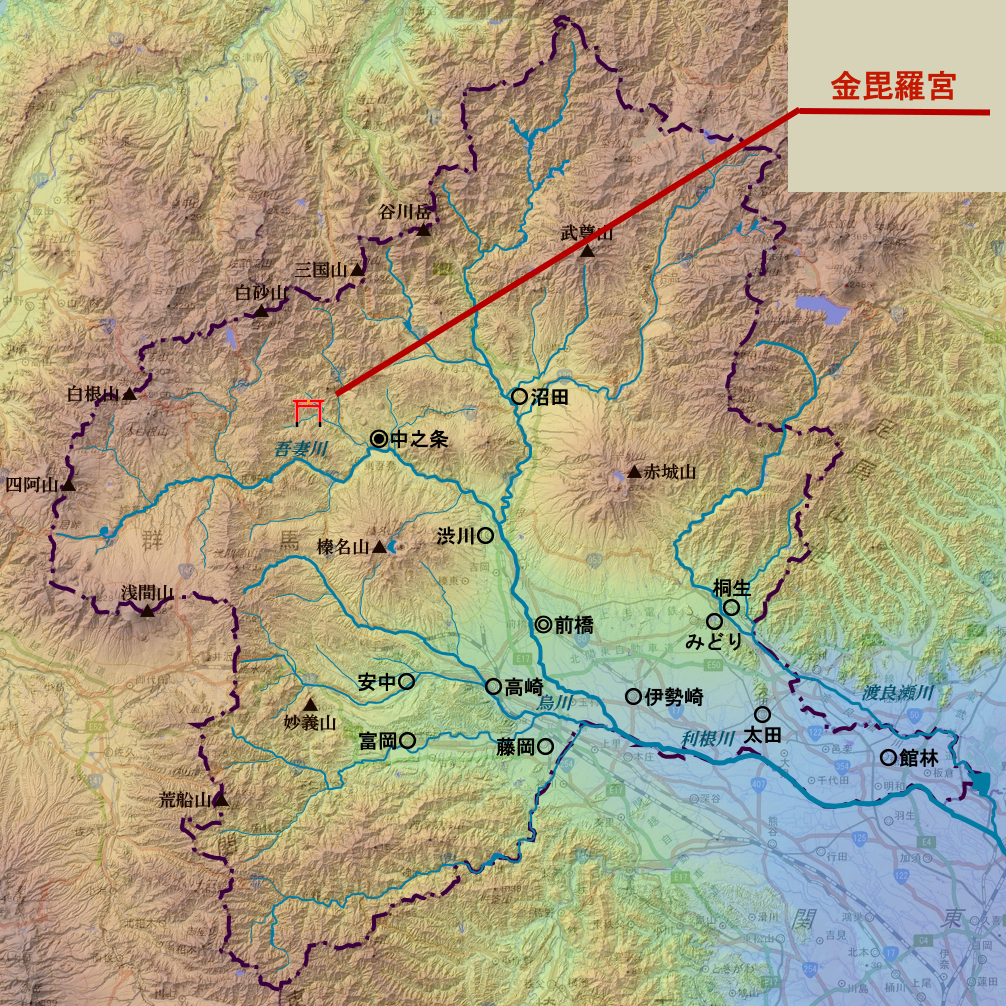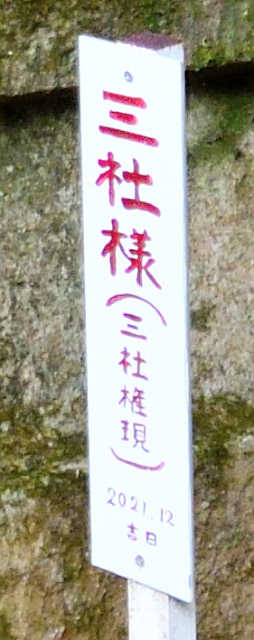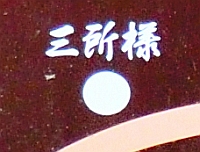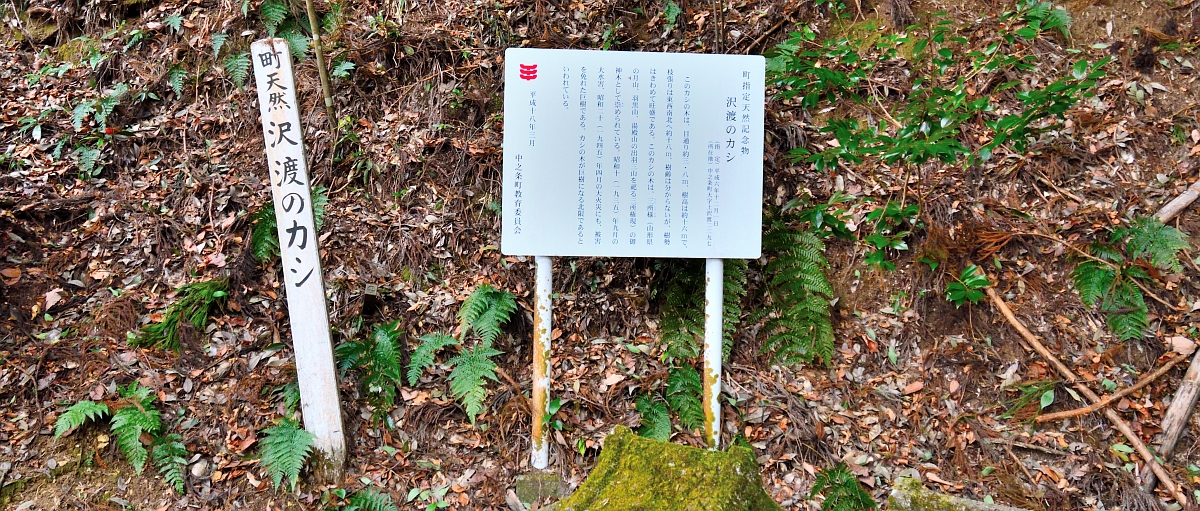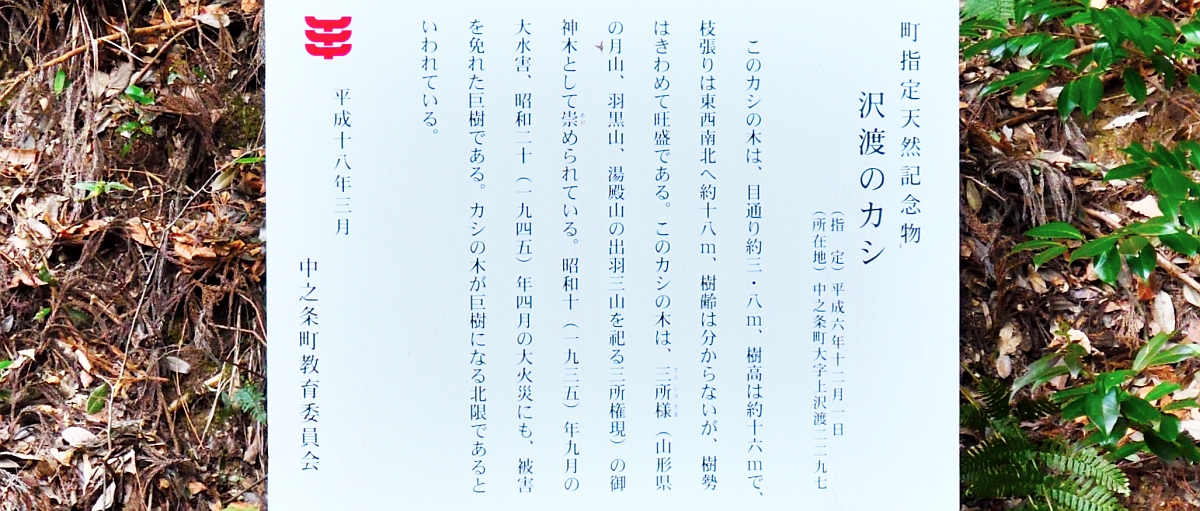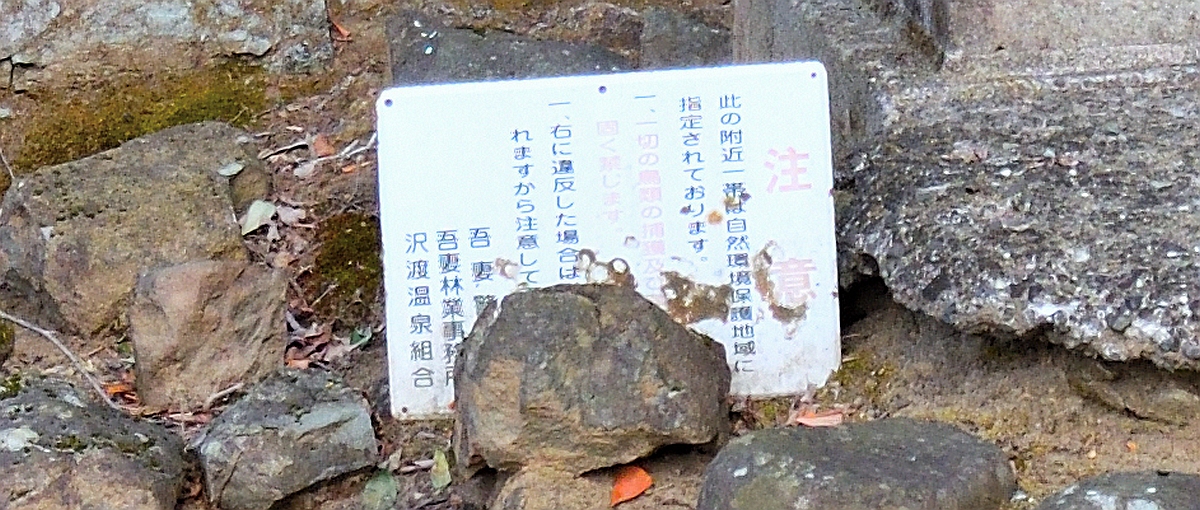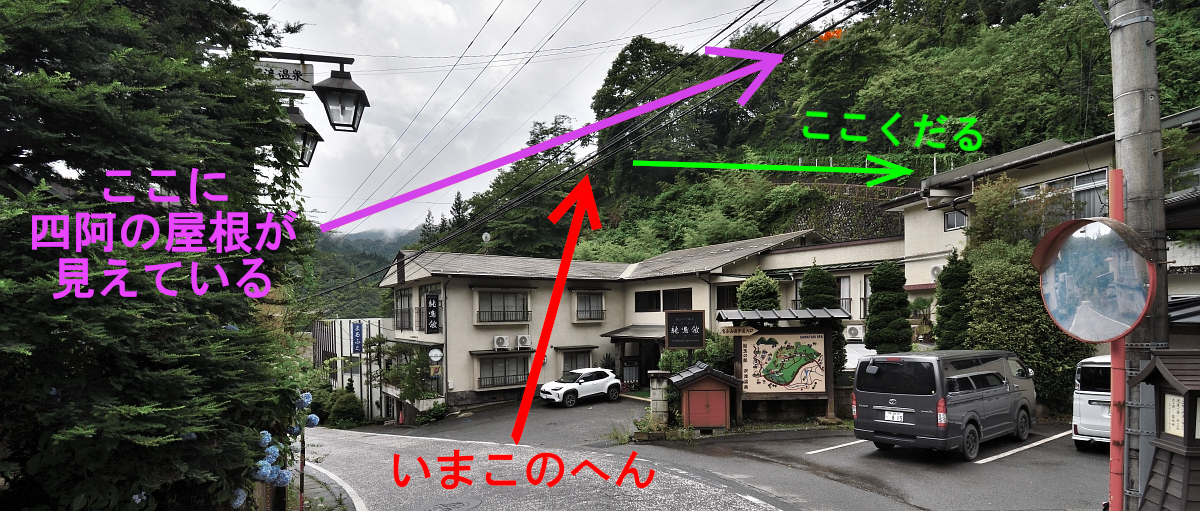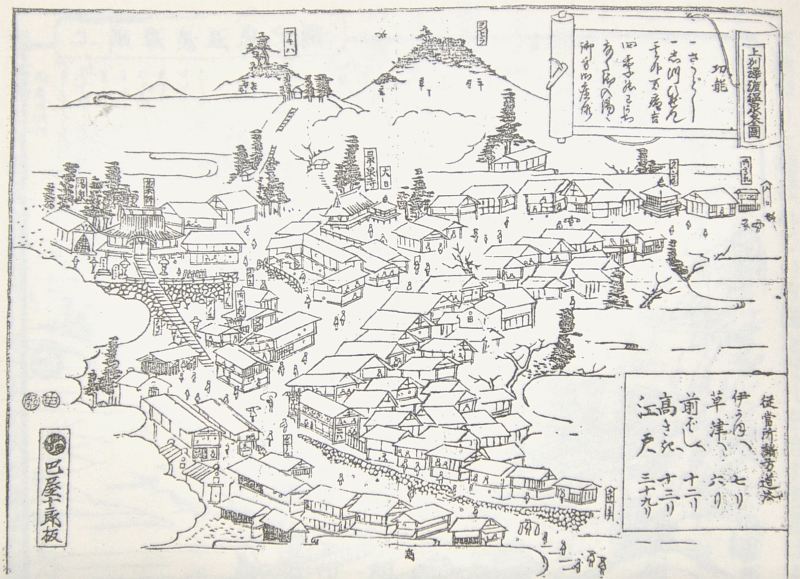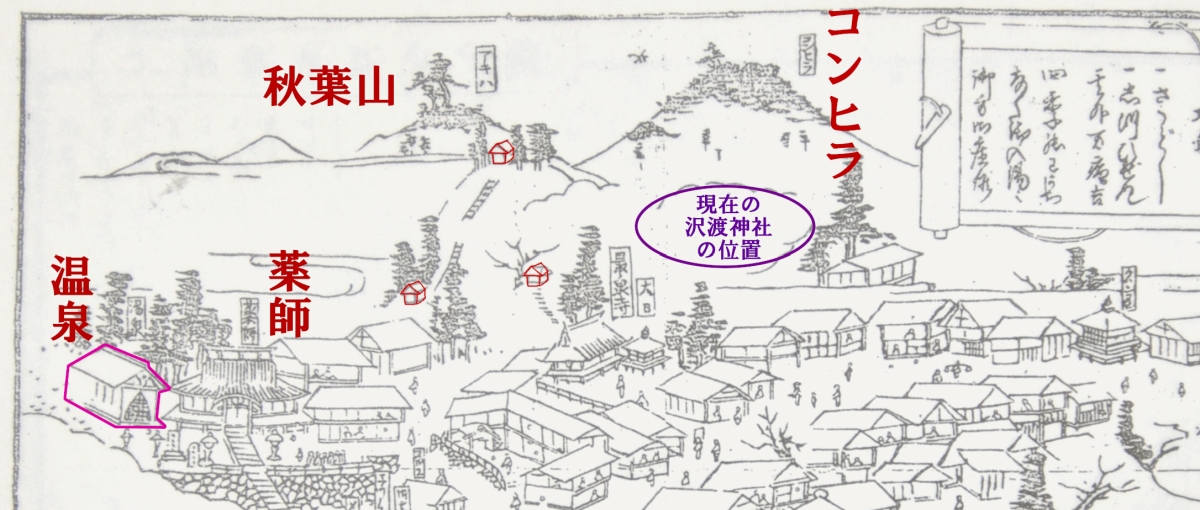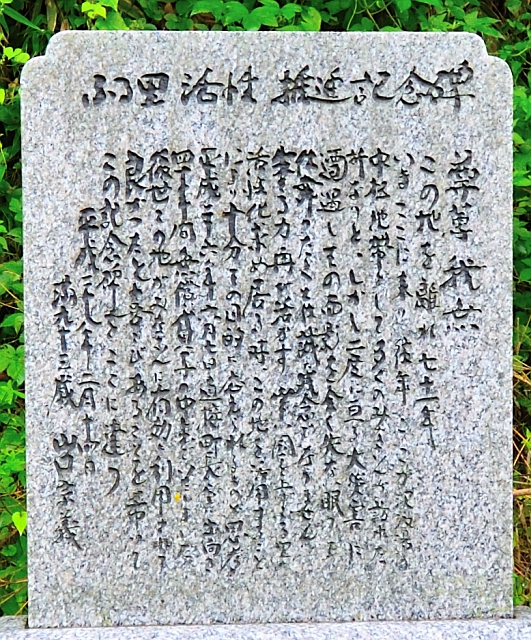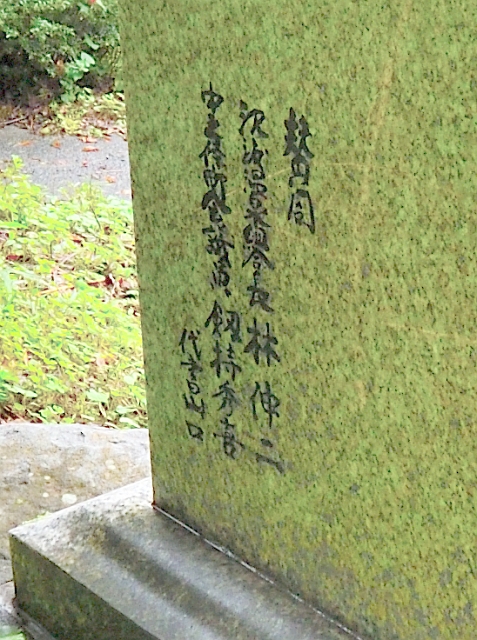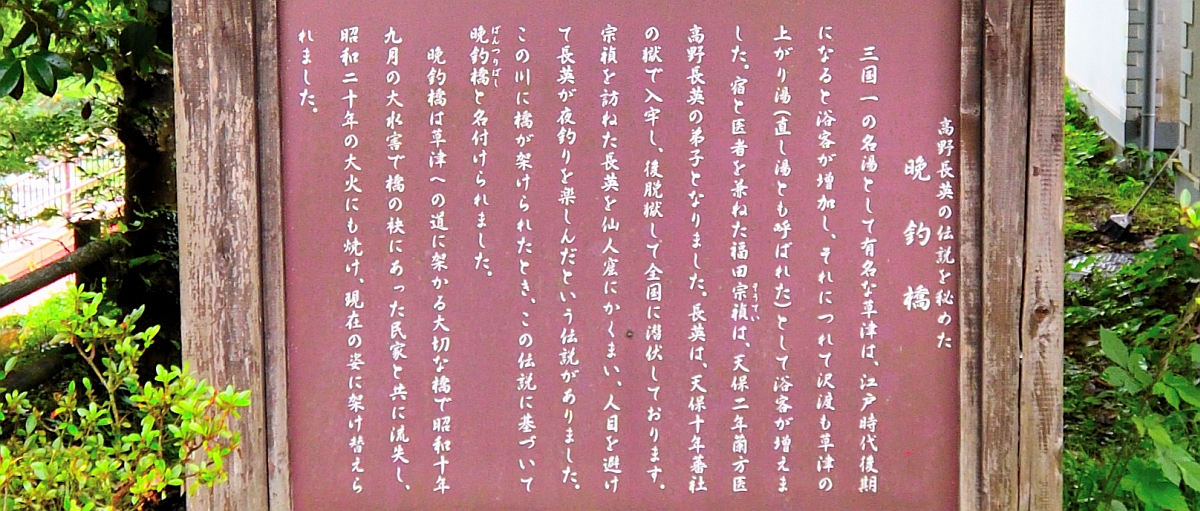| 和暦 |
干支 |
西暦 |
月 |
日 |
事項 |
情報源 |
| 約50万~25万年前 |
榛名山・赤城山の誕生 |
|
| 約225,000年前 |
古榛名山のカルデラ湖(古榛名湖)生成 |
|
| 約 42,000年前 |
古榛名山が大噴火、現榛名湖の誕生 |
|
| 約 35,000年前 |
日本列島での旧石器文化の確実な証拠 |
|
| 約 31,000年前 |
榛名湖の噴火、榛名富士・蛇ヶ岳の生成 |
|
| 約 20,000年前 |
榛名山の噴火、相馬山の生成 |
|
| 約 20,000年前 |
日本列島特有の旧石器文化の普及 |
|
| 約 16,000年前 |
縄文時代はじまる |
|
| |
細尾岩陰遺跡(縄文時代早期)
久森環状列石(縄文時代中期) |
|
| 約 10,000年前 |
榛名山の噴火、水沢山の生成 |
|
| |
|
|
| 神武帝元年 |
辛酉 |
紀元前660年 |
神武天皇即位年とする(皇紀元年) |
戦前皇国史観 |
| |
|
|
|
|
| 崇神天皇48年 |
辛未 |
紀元前611年 |
豊城入彦命(上毛野氏・下毛野氏の祖)が東国を治める |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
57 |
|
|
|
|
「漢委奴国王」印 |
『後漢書』「東夷伝」 |
| 景行天皇40年 |
庚戌 |
110 |
|
|
|
|
日本武尊が碓日の坂を経由して上野国を去る |
|
| 景行天皇55年 |
乙丑 |
125 |
2 |
月 |
|
|
彦狭島王が東山道15国の都督として下向するも、道中病死し上野国に埋葬 |
『日本書紀』 |
| 景行天皇56年 |
丙寅 |
126 |
|
|
|
|
御諸別王(豊城入彦命の3世孫)が東国を治める |
『日本書紀』 |
| 応神天皇15年 |
甲辰 |
284 |
|
|
|
|
荒田別・巫別(両者とも上毛野氏の祖)が百済に使者として派遣される |
『日本書紀』 |
| この頃 |
|
|
|
|
|
|
毛野国が上毛野国と下毛野国に分割となる |
|
| 仁徳天皇53年 |
乙丑 |
365 |
|
|
|
|
上毛野氏の一族、田道が新羅に派遣され、新羅軍を破る |
|
| 仁徳天皇55年 |
丁卯 |
367 |
|
|
|
|
田道が蝦夷と戦い敗死 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 紀元前3~5世紀頃 |
弥生時代はじまる |
|
| |
有笠山遺跡(弥生時代中期) |
|
| |
|
489 |
|
|
|
|
榛名山北部で大噴火、二ツ岳の生成 |
|
| |
丁亥 |
507 |
2 |
月 |
4 |
日 |
継体天皇即位 |
|
| |
|
525~550 |
榛名山北部・二ツ岳で大噴火、榛名山北部吾妻地方の文明が壊滅、毛野国衰退 |
|
| 宣化天皇03年 |
戊午 |
538 |
|
|
|
|
仏教伝来(552年説あり) |
|
| 用明天皇02年 |
丁未 |
587 |
|
|
|
|
仏教派の蘇我馬子が神道派の物部守屋を滅ぼす |
|
| 推古天皇09年 |
辛酉 |
601 |
|
|
|
|
新羅の間諜・迦摩多が上毛野国に配流 |
|
| 推古天皇35年 |
丁亥 |
627 |
|
|
|
|
信濃国から蠅の大群が襲来 |
|
| 舒明天皇09年 |
丁酉 |
637 |
|
|
|
|
上毛野君形名が蝦夷反乱を討伐 |
|
| 大化 |
元 |
年 |
乙巳 |
645 |
6 |
月 |
|
|
大化の改新 |
|
| 〃 |
2 |
年 |
丙午 |
646 |
|
|
|
|
榛名山大噴火 岡崎方面で大被害 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
この頃に吾妻郡設置か |
|
| 斉明天皇04年 |
戊午 |
658 |
|
|
|
|
有馬皇子の変に際し、守大石らが上毛野国に配流 |
|
| 天智天皇02年 |
癸亥 |
663 |
|
|
|
|
上毛野君稚子が新羅征伐の将に任じられる |
|
| 天武天皇元年 |
壬申 |
672 |
|
|
|
|
壬申の乱 |
|
| 天武天皇13年 |
甲申 |
684 |
|
|
|
|
上毛野君が朝臣の姓を賜る |
|
| 大宝 |
元 |
年 |
辛丑 |
701 |
3 |
月 |
21 |
日 |
「大宝律令」成立 |
|
| 〃 |
3 |
年 |
癸卯 |
703 |
3 |
月 |
17 |
日 |
上野国で疫病 |
『続日本紀』 |
| 和銅 |
3 |
年 |
庚戌 |
710 |
3 |
月 |
10 |
日 |
平城京遷都 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
辛亥 |
711 |
3 |
月 |
6 |
日 |
上野国に多胡郡を設置 |
多胡碑 |
| 〃 |
5 |
年 |
壬子 |
712 |
1 |
月 |
28 |
日 |
『古事記』成立 |
|
| 養老 |
4 |
年 |
庚申 |
720 |
5 |
月 |
21 |
日 |
『日本書紀』完成 |
|
| 天平年間 |
729 ~ 749 |
『万葉集』に「左和多里」(さわたり)を詠んだ歌が掲載 |
|
| 天平 |
13 |
年 |
辛巳 |
741 |
|
|
|
|
榛名山二ツ岳噴火 |
|
| 天平宝字4年 |
庚子 |
760 |
3 |
月 |
26 |
日 |
上野国で飢饉、朝廷が救援 |
『続日本紀』 |
| 天平宝字8年 |
甲辰 |
764 |
10 |
月 |
20 |
日 |
上毛野朝臣馬長が上野国司となる |
『続日本紀』 |
| 神護景雲2年 |
戊申 |
768 |
6 |
月 |
6 |
日 |
掌膳采女佐位朝臣老刀自を上野国国造に任じる |
『続日本紀』 |
| 天応 |
元 |
年 |
辛酉 |
781 |
|
|
|
|
桓武天皇が即位 |
|
| 延暦 |
4 |
年 |
乙丑 |
789 |
|
|
|
|
「吾妻七騎」が坂上田村麻呂の東征軍に加わったと伝わる(~804)
率いたのは小野金善とも |
『中之条町誌』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
9 |
年 |
庚午 |
790 |
|
|
|
|
上野国など14国で飢饉 |
|
| 〃 |
13 |
年 |
甲戌 |
794 |
10 |
月 |
22 |
日 |
平安京遷都 |
|
| 弘仁 |
2 |
年 |
辛卯 |
811 |
2 |
月 |
15 |
日 |
上野国が「上国」から「大国」に格上げ |
『日本後紀』 |
| 天長 |
3 |
年 |
丙午 |
826 |
9 |
月 |
6 |
日 |
上野国が親王任国となる |
『類聚三代格』 |
| 承和 |
元 |
年 |
甲寅 |
834 |
3 |
月 |
21 |
日 |
阿保親王が上野国国司となる |
『続日本後紀』 |
| 貞観 |
4 |
年 |
壬午 |
862 |
|
|
|
|
吾妻郡擬少領上毛野坂本朝臣真道の名が文書に記載 |
『政事要略』 |
| 〃 |
9 |
年 |
丁亥 |
867 |
6 |
月 |
20 |
日 |
上野国赤城神社・榛名神社などの神階格上げ |
『三代実録』 |
| 仁和 |
元 |
年 |
乙巳 |
885 |
|
|
|
|
上野国で班田制が崩壊 |
|
| 延喜 |
13 |
年 |
癸酉 |
913 |
|
|
|
|
『延喜式』に上野国9牧記載 |
|
| 延長 |
5 |
年 |
丁亥 |
927 |
|
|
|
|
『延喜式』巻9・10「神名帳」成立 |
|
| 承平 |
5 |
年 |
乙未 |
935 |
|
|
|
|
平将門の乱(承平の乱、~940) |
|
| 天慶 |
2 |
年 |
己亥 |
939 |
12 |
月 |
|
|
藤原純友の乱(天慶の乱、~941) |
|
| 天暦 |
元 |
年 |
丁未 |
947 |
|
|
|
|
市代牧から「白波」など名馬を朝廷へ献上 |
|
| 永承 |
6 |
年 |
辛卯 |
1051 |
|
|
|
|
前九年の役 |
|
| 永保 |
3 |
年 |
癸亥 |
1083 |
|
|
|
|
後三年の役 |
|
| 天仁 |
元 |
年 |
戊子 |
1108 |
7 |
月 |
21 |
日 |
浅間山大噴火 |
|
| 保元 |
元 |
年 |
丙子 |
1156 |
|
|
|
|
保元の乱 |
|
| 平治 |
元 |
年 |
己卯 |
1159 |
|
|
|
|
平治の乱 |
|
| 養和 |
2 |
年 |
壬寅 |
1182 |
1 |
月 |
|
|
「吾妻八郎」が栗毛馬1頭を伊勢神宮へ奉納 |
『吾妻鏡』 |
| 文治 |
元 |
年 |
乙巳 |
1185 |
3 |
月 |
24 |
日 |
壇ノ浦の戦い、平家滅亡 |
|
| 建久 |
2 |
年 |
辛亥 |
1191 |
8 |
月 |
15 |
日 |
澤渡神社の前身、湯前神社創建 |
|
| 〃 |
3 |
年 |
壬子 |
1192 |
7 |
月 |
12 |
日 |
源頼朝が征夷大将軍となる |
|
| 〃 |
4 |
年 |
癸丑 |
1193 |
|
|
|
|
源頼朝・三原荘での巻狩伝説 |
|
| 承久 |
3 |
年 |
辛巳 |
1221 |
|
|
|
|
承久の乱(吾妻太郎討死) |
|
| 仁治 |
2 |
年 |
辛丑 |
1241 |
3 |
月 |
20 |
日 |
三原荘(上野国)と長倉保(信濃国)の境界を巡り、武田信光と海野幸氏の総論 |
『吾妻鏡』 |
| 康元 |
元 |
年 |
丙辰 |
1256 |
6 |
月 |
|
|
上野国守護の安達泰盛が評定衆に加わる |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
|
|
長尾景煕が白井荘を与えられ、白井城を築城 |
|
| 文永 |
7 |
年 |
庚午 |
1270 |
12 |
月 |
|
|
沢渡温泉の図像板碑 |
|
| 〃 |
8 |
年 |
辛未 |
1271 |
|
|
|
|
林昌寺(中之条伊勢町)板碑 |
|
| 〃 |
11 |
年 |
甲戌 |
1274 |
10 |
月 |
|
|
蒙古襲来(文永の役) |
|
| 弘安 |
3 |
年 |
庚辰 |
1280 |
|
|
|
|
一遍上人が上野国に来訪 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
辛巳 |
1281 |
5 |
月 |
|
|
蒙古襲来(弘安の役) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
8 |
年 |
乙酉 |
1285 |
11 |
月 |
|
|
霜月騒動 上野国守護安達泰盛と上野国の御家人が破れ、北条得宗家が上野国守護となる |
|
| 永仁 |
6 |
年 |
戊戌 |
1296 |
|
|
|
|
『上野国神名帳』に吾妻郡13座を所載 |
|
| 建武 |
元 |
年 |
甲戌 |
1334 |
|
|
|
|
建武の新政 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
月 |
|
|
後醍醐天皇が護良親王・新田義貞・楠木正成らに足利尊氏討伐を命じる |
|
| 延元 |
2 |
年 |
丁丑 |
1338 |
|
|
|
|
新田義貞が越前国で討死(建武4年) |
|
| 貞和 |
5 |
年 |
己丑 |
1349 |
5 |
月 |
5 |
日 |
北朝方の吾妻太郎行盛が、南朝方の里見氏に攻められ敗死したとの伝承 |
|
| 観応 |
元 |
年 |
庚寅 |
1350 |
|
|
|
|
観応の擾乱(~1352)(正平5年) |
|
| 延文年間 |
|
1356~1361 |
『神道集』成立、「和利宮」の初出 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 応永 |
2 |
年 |
乙亥 |
1395 |
7 |
月 |
24 |
日 |
上杉憲定が上野国守護となる |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
23 |
年 |
丙申 |
1416 |
|
|
|
|
上杉禅秀の乱 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 永享 |
10 |
年 |
戊午 |
1438 |
|
|
|
|
永享の乱 足利持氏と上杉憲実が対立 長尾景仲が関東管領上杉憲実を白井城に移す |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
吾妻氏家臣の三家が主家を抑えて吾妻地方を分割、中之条は塩谷氏が支配 |
|
| 享徳 |
3 |
年 |
甲戌 |
1455 |
|
|
|
|
享徳の乱はじまる(~1483) 関東管領上杉憲忠が暗殺される |
|
| 応仁 |
元 |
年 |
丁亥 |
1467 |
5 |
月 |
26 |
日 |
応仁の乱はじまる |
|
| 文明 |
5 |
年 |
癸巳 |
1473 |
|
|
|
|
塩谷氏と大野氏が争う |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
この頃、吾妻33番観音が成立という |
|
| 〃 |
8 |
年 |
丙申 |
1476 |
|
|
|
|
長尾景春の乱 関東管領上杉顕定に叛く |
|
| 〃 |
12 |
年 |
庚子 |
1480 |
|
|
|
|
吾妻方面の諸将が平井城・上杉顕定に服属 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
関憲勝が大岩郷に転住 |
|
| 〃 |
14 |
年 |
壬寅 |
1482 |
11 |
月 |
27 |
日 |
都鄙和睦 享徳の乱の終結 |
|
| 〃 |
18 |
年 |
丙午 |
1486 |
|
|
|
|
京都常光院の堯恵が草津温泉・伊香保温泉に逗留 |
北国紀行 |
| 文亀 |
2 |
年 |
壬戌 |
1502 |
|
|
|
|
連歌師の宗祇が伊香保温泉に逗留 |
宗祇終焉記 |
| 永正 |
7 |
年 |
庚午 |
1510 |
7 |
月 |
|
|
上杉顕定討死 養子の上杉憲房が白井城に入る |
|
| 〃 |
10 |
年 |
癸酉 |
1513 |
4 |
月 |
|
|
箕輪城長野憲業が大戸浦野氏を攻略を榛名山に祈願 |
榛名山文書 |
| 大永 |
3 |
年 |
癸未 |
1523 |
|
|
|
|
関氏が大岩不動尊を建立 |
『中之条町誌』 |
| 享禄 |
3 |
年 |
庚寅 |
1530 |
11 |
月 |
7 |
日 |
箕輪城長野憲業が吾妻で討死 業正が後継 |
|
| 天文 |
15 |
年 |
丙午 |
1546 |
|
|
|
|
河越夜戦 関東管領上杉憲政が北条氏康に大敗し平井城へ退く |
|
| 〃 |
20 |
年 |
辛亥 |
1551 |
|
|
|
|
北条氏康が上野国へ侵攻、平井城上杉憲政を破る |
|
| 〃 |
21 |
年 |
壬子 |
1552 |
1 |
月 |
10 |
日 |
上杉憲政が平井城を出奔、越後国上杉謙信を頼る |
|
| 弘治 |
3 |
年 |
丁巳 |
1557 |
2 |
月 |
2 |
日 |
『上野国神名帳』の写本が現存 |
|
| 永禄 |
3 |
年 |
庚申 |
1560 |
8 |
月 |
29 |
日 |
上杉謙信が上野国へ侵入 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
辛酉 |
1561 |
3 |
月 |
|
|
上杉謙信が北条氏の相模国小田原城を包囲 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
月 |
21 |
日 |
箕輪城主長野業正が没し、業盛が後継となる |
|
| 〃 |
6 |
年 |
癸亥 |
1563 |
10 |
月 |
|
|
真田氏が斎藤憲広(または基国)を破り、憲広は越後へ逃れる |
|
| 〃 |
8 |
年 |
乙丑 |
1565 |
10 |
月 |
|
|
武田氏が嵩山城を攻め落とし、斎藤氏滅亡 |
|
| 〃 |
9 |
年 |
丙寅 |
1566 |
8 |
月 |
|
|
上杉謙信、沼田城から吾妻郡方面攻略 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
武田信玄が箕輪城の長野氏を滅ぼす |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
武田氏麾下の海野氏が吾妻方面の郡代に任ぜられる |
|
| 〃 |
12 |
年 |
己巳 |
1569 |
|
|
|
|
北条氏と上杉氏が和睦、上野国は上杉氏領となる |
|
| 元亀 |
2 |
年 |
辛未 |
1571 |
|
|
|
|
武田信玄配下の真田氏が上野国白井城を攻略 |
|
| 〃 |
3 |
年 |
壬申 |
1572 |
|
|
|
|
武田家が白井城を攻め落とす |
|
| 〃 |
4 |
年 |
癸酉 |
1573 |
4 |
月 |
12 |
日 |
武田信玄没 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
|
|
織田信長が足利義昭を京都から追放(室町幕府の滅亡) |
|
| 天正 |
元 |
年 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
上杉謙信が上野国白井城を攻略 |
|
| 〃 |
3 |
年 |
乙亥 |
1575 |
5 |
月 |
21 |
日 |
長篠の戦い 武田氏の勢力衰える 吾妻方面の将兵多数討死と云う |
|
| 〃 |
4 |
年 |
丙子 |
1576 |
|
|
|
|
真田昌幸が岩櫃城に入城 |
|
| 〃 |
7 |
年 |
己卯 |
1579 |
|
|
|
|
武田勝頼と上杉景勝が和睦し、上野国は武田家・信濃国は上杉家と定める |
|
| 〃 |
8 |
年 |
庚辰 |
1580 |
5 |
月 |
23 |
日 |
真田昌幸による沼田城攻略 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
月 |
7 |
日 |
武田勝頼が真田昌幸を沼田へ帰城させる |
|
| 〃 |
10 |
年 |
壬午 |
1582 |
3 |
月 |
11 |
日 |
武田勝頼が天目山で自害、武田氏滅亡 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
3 |
月 |
23 |
〃 |
織田信長が上野国を滝川一益に与える |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
6 |
月 |
2 |
〃 |
本能寺の変 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
天正壬午の乱(上野国などを巡る徳川・北条・上杉氏の争乱) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
|
|
北条氏が大戸方面から吾妻郡へ侵攻 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
29 |
〃 |
徳川家康と北条氏直が講和(天正壬午の乱終結) |
|
| 〃 |
11 |
年 |
丁亥 |
1583 |
5 |
月 |
8 |
日 |
豊臣秀吉、九州平定 |
|
| 〃 |
15 |
年 |
丁亥 |
1587 |
5 |
月 |
8 |
日 |
近衛前久が草津温泉で湯治 |
|
| 〃 |
17 |
年 |
己丑 |
1589 |
7 |
月 |
21 |
日 |
秀吉が上野国沼田を北条家へ、名胡桃城を真田家へ仕置 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
吾妻合戦 |
|
| 〃 |
18 |
年 |
庚寅 |
1590 |
2 |
月 |
|
|
中之条古城が落城 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
|
|
秀吉による小田原攻めに伴い、上野国の北条方の諸城も攻略 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
15 |
日 |
真田信幸が沼田に入り沼田藩創始 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
秋 |
|
|
|
吾妻郡の諸城を破却 |
|
| 文禄 |
元 |
年 |
壬辰 |
1592 |
|
|
|
|
朝鮮出兵(文禄の役) |
|
| 慶長 |
5 |
年 |
庚子 |
1600 |
9 |
月 |
15 |
日 |
関ヶ原の合戦 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 元和 |
元 |
年 |
乙卯 |
1615 |
5 |
月 |
|
|
大坂夏の陣 |
|
| 〃 |
2 |
年 |
丙辰 |
1616 |
|
|
|
|
真田氏、岩櫃城を破却し、原町に奉行所を開設、中之条に屋敷割り |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
真田信幸が上田に移り、長男・真田信吉に沼田城3万石を与える(沼田藩2代目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寛永 |
2 |
年 |
乙丑 |
1625 |
|
|
|
|
中之条町を王子原に町割り、用水開削 |
|
| 〃 |
11 |
年 |
甲戌 |
1634 |
|
|
|
|
真田信吉が吾妻地方の知行替えを実施 |
|
| 明暦 |
2 |
年 |
丙申 |
1656 |
|
|
|
|
真田信直(信吉の次男)が沼田藩を継ぐ(沼田藩5代目) |
|
| 延宝 |
7 |
年 |
己未 |
1679 |
|
|
|
|
藩主真田信直が沢渡温泉に入湯 |
|
| 〃 |
8 |
年 |
庚申 |
1680 |
|
|
|
|
慶寿院(真田信直の母)が沢渡温泉に入湯 |
|
| 天和 |
元 |
年 |
辛酉 |
1681 |
11 |
月 |
|
|
沼田藩真田信直が改易、天領となる |
|
| 貞享 |
3 |
年 |
丙寅 |
1686 |
|
|
|
|
検地帳に「薬師堂」記載 |
|
| 元禄 |
3 |
年 |
庚午 |
1690 |
|
|
|
|
吾妻33観音札所再興 |
|
| 〃 |
11 |
年 |
戊寅 |
1698 |
|
|
|
|
中之条東部が旗本保科氏の支配となり、伊勢町根岸家を代官とする |
|
| 宝永 |
2 |
年 |
戊子 |
1705 |
|
|
|
|
本多正永(伯耆守)が藩主となり、沼田藩復活(沼田藩Ⅱ初代) |
|
| 〃 |
7 |
年 |
庚寅 |
1710 |
10 |
月 |
|
|
沢渡温泉、従来の「上の湯」「下の湯」に加えて「中の湯」開設 |
|
| 享保 |
元 |
年 |
丙申 |
1716 |
3 |
月 |
|
|
巡見使が山田、上沢渡経由で草津へ向かう |
|
| 〃 |
15 |
年 |
庚戌 |
1730 |
|
|
|
|
沼田藩主・本多正矩が駿河田中藩へ転出、沼田は天領となる |
|
| 安永 |
8 |
年 |
己亥 |
1779 |
|
|
|
|
中之条大火 |
|
| 天明 |
3 |
年 |
癸卯 |
1783 |
7 |
月 |
7 |
日 |
浅間山大噴火(天明の浅間焼け) |
|
| 享和 |
3 |
年 |
癸亥 |
1803 |
7 |
月 |
|
|
沢渡温泉湯宿経営者3名が蘭医福田宗禎(喜左衛門)を訴える |
|
| 文化 |
3 |
年 |
丙寅 |
1806 |
|
|
|
|
10年に一度の豊作となる |
|
| 文政 |
3 |
年 |
庚辰 |
1820 |
|
|
|
|
十辺舎一九『東海道中膝栗毛』シリーズ「上州草津温泉道中」に暮坂峠・沢渡温泉が登場 |
|
| 〃 |
8 |
年 |
乙酉 |
1825 |
2 |
月 |
18 |
日 |
異国船打払令 |
|
| 〃 |
11 |
年 |
戊子 |
1828 |
|
|
|
|
富田永世が四万温泉・沢渡温泉に入湯 |
|
| 天保 |
2 |
年 |
辛卯 |
1831 |
|
|
|
|
江戸の医者・蘭学者の高野長英が沢渡の蘭医・福田宗禎を訪問 |
|
| 〃 |
8 |
年 |
丁酉 |
1837 |
2 |
月 |
|
|
大塩平八郎の乱 |
|
| 〃 |
10 |
年 |
己亥 |
1839 |
|
|
|
|
高野長英ら蘭学者が捕縛(蛮社の獄) |
|
| 弘化 |
元 |
年 |
甲辰 |
1844 |
|
|
|
|
牢の火災に乗じて高野長英が脱獄。以後「沢渡温泉に潜伏した」との伝説がある |
|
| 嘉永 |
6 |
年 |
癸丑 |
1853 |
6 |
月 |
3 |
日 |
ペリー、浦賀に来航 |
|
| 安政 |
元 |
年 |
甲寅 |
1854 |
2 |
月 |
25 |
日 |
吾妻川の通船許可 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
3 |
〃 |
3 |
〃 |
日米和親条約、下田・箱館を開港 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
村明細帳に「上沢渡村」と記載 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
丁巳 |
1857 |
8 |
月 |
15 |
日 |
神社再建 |
|
| 〃 |
5 |
年 |
戊午 |
1858 |
6 |
月 |
19 |
日 |
大老井伊直弼、独断で日米修好通商条約を締結 |
|
| 文久 |
元 |
年 |
辛酉 |
1861 |
11 |
月 |
10 |
日 |
和宮降嫁、中山道を通過 |
|
| 元治 |
元 |
年 |
甲子 |
1864 |
|
|
|
|
道陸神峠を開削し、馬1匹通行可能とする |
|
| 慶応 |
3 |
年 |
丁卯 |
1867 |
10 |
月 |
14 |
日 |
徳川慶喜が大政奉還を上奏 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
戊辰 |
1868 |
1 |
月 |
3 |
日 |
鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
神仏分離令 |
|
| 明治 |
元 |
年 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
8 |
日 |
明治改元 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
上沢渡村薬師堂から薬師如来を湯原の観音堂に遷す |
|
| 〃 |
2 |
年 |
己巳 |
1869 |
6 |
月 |
|
|
版籍奉還 |
|
| 〃 |
4 |
年 |
辛未 |
1871 |
7 |
月 |
14 |
日 |
廃藩置県 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
10 |
日 |
大区小区制施行 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
社格制度創設 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
2 |
日 |
太陰暦から新暦に切り替え(12月3日が明治6年1月1日となる) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
25 |
日 |
市制・町村制施行 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
湯原の観音堂を湯前神社と改称 |
|
| 〃 |
5 |
年 |
壬申 |
1872 |
11 |
月 |
|
|
群馬県で地蔵・観音像・庚申塚・十三夜塔・馬頭観世音などの撤去命令が出る |
|
| 〃 |
10 |
年 |
丁丑 |
1877 |
|
|
|
|
文人・野口常共が沢渡温泉の福田宗禎邸に逗留、沢渡八勝詩序を著す |
|
| 〃 |
11 |
年 |
戊寅 |
1878 |
7 |
月 |
22 |
日 |
郡区町村編制法を領布 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
中之条に吾妻郡役所が開設 |
|
| 〃 |
12 |
年 |
己卯 |
1879 |
|
|
|
|
スウェーデン探検家ノルデンショルドとデンマーク探検家ホウゴーが沢渡温泉を訪れる |
|
| 〃 |
17 |
年 |
甲申 |
1884 |
6 |
月 |
25 |
日 |
上野=高崎間に鉄道開業、式典に明治天皇行幸 |
|
| 〃 |
20 |
年 |
丁亥 |
1887 |
2 |
月 |
|
|
内務大臣井上馨が沢渡に来訪 |
|
| 〃 |
22 |
年 |
己丑 |
1889 |
4 |
月 |
1 |
日 |
町村制により、下沢渡・上沢渡・四万・折田・山田5ヶ村が合併して吾妻郡沢田となる |
|
| 〃 |
27 |
年 |
甲午 |
1894 |
7 |
月 |
25 |
日 |
豊島沖海戦(日清戦争開戦) |
|
| 〃 |
28 |
年 |
乙未 |
1895 |
4 |
月 |
17 |
日 |
下関条約(日清戦争終結) |
|
| 〃 |
29 |
年 |
丙申 |
1896 |
3 |
月 |
29 |
日 |
郡の再編により、吾妻郡設置 |
|
| 〃 |
31 |
年 |
戊戌 |
1898 |
11 |
月 |
|
|
暮坂峠の新道を開削 |
|
| 〃 |
35 |
年 |
壬寅 |
1902 |
1 |
月 |
30 |
日 |
日英同盟 |
|
| 〃 |
37 |
年 |
甲辰 |
1904 |
2 |
月 |
10 |
日 |
ロシアに宣戦布告(日露戦争開戦) |
|
| 〃 |
38 |
年 |
乙巳 |
1905 |
3 |
月 |
1 |
日 |
奉天会戦はじまる(第七師団派遣) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
5 |
日 |
ポーツマス条約(日露戦争終結) |
|
| 〃 |
40 |
年 |
丁未 |
1907 |
1 |
月 |
|
|
郡内で神社の合併が盛んになる |
|
| 〃 |
41 |
年 |
戊申 |
1908 |
6 |
月 |
22 |
日 |
上沢渡地区の諸社を湯前神社に合併 |
|
| 〃 |
42 |
年 |
己酉 |
1909 |
5 |
月 |
21 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
7 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
10 |
月 |
17 |
日 |
鯉沢(渋川)=中之条に鉄道敷設 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
4 |
日 |
前橋=渋川間に電鉄開業 |
|
| 〃 |
43 |
年 |
庚戌 |
1910 |
12 |
月 |
25 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
44 |
年 |
辛亥 |
1911 |
5 |
月 |
8 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
3 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
45 |
年 |
壬子 |
1912 |
|
|
|
|
湯前神社(後の沢渡神社)移転のため、天神山を造成 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
5 |
月 |
27 |
日 |
移転許可 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
この頃、通称「湯前神社」「温泉神社」を「沢渡神社」に改号 |
|
| 〃 |
〃 |
年 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
30 |
日 |
明治天皇、崩御 |
|
| 大正 |
元 |
年 |
〃 |
1912 |
7 |
月 |
30 |
日 |
大正改元 |
|
| 〃 |
3 |
年 |
甲寅 |
1914 |
4 |
月 |
|
|
天神山に遷宮、社殿建立 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
7 |
月 |
28 |
日 |
第一次世界大戦勃発 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
12 |
日 |
神饌幣帛料供進神社に指定 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
11 |
月 |
10 |
日 |
大正天皇即位大礼 |
|
| 〃 |
7 |
年 |
戊午 |
1918 |
|
|
|
|
シベリア出兵(~1922) |
|
| 〃 |
8 |
年 |
己未 |
1919 |
6 |
月 |
28 |
日 |
ベルサイユ条約締結(第一次世界大戦終結) |
|
| 〃 |
9 |
年 |
庚申 |
1920 |
11 |
月 |
|
|
渋川=中之条間の鉄道が電車となる(長野原線) |
|
| 〃 |
10 |
年 |
辛酉 |
1921 |
7 |
月 |
1 |
日 |
上越南線・高崎=渋川間開業 |
|
| 〃 |
11 |
年 |
壬戌 |
1922 |
|
|
|
|
若山牧水、草津・花敷・沢渡温泉へ |
|
| 〃 |
12 |
年 |
癸亥 |
1923 |
9 |
月 |
1 |
日 |
関東大震災 |
|
| 〃 |
15 |
年 |
丙寅 |
1926 |
9 |
月 |
18 |
日 |
草津電鉄(草津=軽井沢)開通 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
25 |
日 |
大正天皇崩御 |
|
| 昭和 |
元 |
年 |
〃 |
1926 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
昭和改元 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
3 |
年 |
戊辰 |
1928 |
11 |
月 |
10 |
日 |
昭和天皇即位大礼 |
|
| 〃 |
5 |
年 |
庚午 |
1930 |
|
|
|
|
沢渡温泉の字湯御堂谷戸の畑で1270年の銘が入る図像板碑出土 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
12 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
6 |
年 |
辛未 |
1931 |
9 |
月 |
1 |
日 |
上越線全通 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
18 |
日 |
柳条湖事件(満州事変開始) |
|
| 〃 |
10 |
年 |
乙亥 |
1935 |
9 |
月 |
26 |
日 |
豪雨による土砂災害で、沢渡温泉で死者23名、ほか上沢渡各集落地で40名死亡 |
|
| 〃 |
12 |
年 |
丁丑 |
1937 |
7 |
月 |
7 |
日 |
日中戦争開戦(盧溝橋事件) |
|
| 〃 |
14 |
年 |
己卯 |
1939 |
8 |
月 |
|
|
沢渡温泉・四万温泉で軍人の特需により大繁盛 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
1 |
日 |
ドイツがポーランドへ侵攻(第二次世界大戦開戦) |
|
| 〃 |
15 |
年 |
庚辰 |
1940 |
11 |
月 |
10 |
日 |
紀元二千六百年記念行事 |
|
| 〃 |
16 |
年 |
辛巳 |
1941 |
12 |
月 |
8 |
日 |
真珠湾攻撃(太平洋戦争開戦) |
|
| 〃 |
17 |
年 |
壬午 |
1942 |
8 |
月 |
|
|
東條英機首相が四万の製炭業を視察 |
|
| 〃 |
19 |
年 |
甲申 |
1944 |
6 |
月 |
6 |
日 |
ノルマンディー上陸作戦 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
10 |
月 |
20 |
日 |
レイテ沖海戦 |
|
| 〃 |
20 |
年 |
乙酉 |
1945 |
1 |
月 |
2 |
日 |
国鉄長野原線・渋川=長野原間の開通(現在の吾妻線) |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
3 |
月 |
10 |
日 |
東京大空襲 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
|
|
|
|
東京大空襲の被災者の児童・引率教師ら211名余りが沢渡温泉に疎開してくる |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
4 |
月 |
16 |
日 |
沢渡大火、114戸焼失・死者5名、沢渡神社全焼 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
5 |
月 |
7 |
日 |
ドイツ降伏 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
15 |
日 |
終戦の詔 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
12 |
月 |
|
|
GHQの神道指令(国家神道・社格の廃止) |
|
| 〃 |
21 |
年 |
丙戌 |
1946 |
2 |
月 |
1 |
日 |
農地改革 |
|
| 〃 |
22 |
年 |
丁亥 |
1947 |
2 |
月 |
2 |
日 |
宗教法人沢渡神社の創立を決定 |
|
| 〃 |
23 |
〃 |
〃 |
1948 |
9 |
月 |
|
|
アイオン台風 四万沢渡方面で落橋多数 |
|
| 〃 |
24 |
年 |
己丑 |
1949 |
5 |
月 |
9 |
日 |
沢田村山火事 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
8 |
月 |
31 |
日 |
キティ台風 群馬県内で死者42名 |
|
| 〃 |
27 |
年 |
壬辰 |
1952 |
8 |
月 |
20 |
日 |
宗教法人沢渡神社創立を申請 |
|
| 〃 |
28 |
年 |
癸巳 |
1953 |
4 |
月 |
|
|
沢渡神社社殿再建 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
9 |
月 |
1 |
日 |
町村合併法制定(昭和31年9月末までの時限立法)、町村合併相次ぐ |
|
| 〃 |
30 |
年 |
乙未 |
1955 |
|
|
|
|
神武景気 |
|
|
|
年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〃 |
33 |
年 |
戊戌 |
1958 |
11 |
月 |
10 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
34 |
年 |
己亥 |
1959 |
4 |
月 |
14 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
36 |
年 |
辛丑 |
1961 |
|
|
|
|
細尾・暮坂峠間に県道開通 |
|
| 〃 |
39 |
年 |
甲辰 |
1964 |
11 |
月 |
7 |
日 |
長野原=草津間に草津有料道路が開通 |
|
| 〃 |
40 |
年 |
乙巳 |
1965 |
12 |
月 |
2 |
日 |
吾妻川支流に草津温泉廃水の中和用の品木ダム完成 |
|
| 〃 |
46 |
年 |
辛亥 |
1971 |
3 |
月 |
7 |
日 |
国鉄吾妻線開業 |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
辛亥 |
〃 |
11 |
月 |
28 |
日 |
上越新幹線起工 |
|
| 〃 |
55 |
年 |
庚申 |
1980 |
4 |
月 |
16 |
日 |
沢渡大火で焼失した金毘羅宮跡地に堂宇を再建 |
|
| 〃 |
56 |
年 |
辛酉 |
1981 |
12 |
月 |
23 |
日 |
上越新幹線の中山トンネル貫通 |
|
| 〃 |
57 |
年 |
壬戌 |
1982 |
11 |
月 |
15 |
日 |
上越新幹線の大宮・新潟間で営業開始 |
|
| 〃 |
60 |
年 |
乙丑 |
1985 |
3 |
月 |
14 |
日 |
上越新幹線が上野駅へ乗り入れ |
|
| 〃 |
〃 |
〃 |
乙丑 |
〃 |
10 |
月 |
2 |
日 |
関越自動車道全通 |
|
| 〃 |
64 |
年 |
己巳 |
1989 |
1 |
月 |
7 |
日 |
昭和天皇崩御 |
|
| 平成 |
元 |
年 |
〃 |
1989 |
1 |
月 |
8 |
日 |
平成改元 |
|
| 〃 |
16 |
年 |
甲申 |
2004 |
9 |
月 |
1 |
日 |
浅間山噴火 |
|
| 〃 |
31 |
年 |
己亥 |
2019 |
4 |
月 |
30 |
日 |
平成天皇が譲位 |
|
| 令和 |
元 |
年 |
〃 |
〃 |
5 |
月 |
1 |
日 |
令和改元 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|